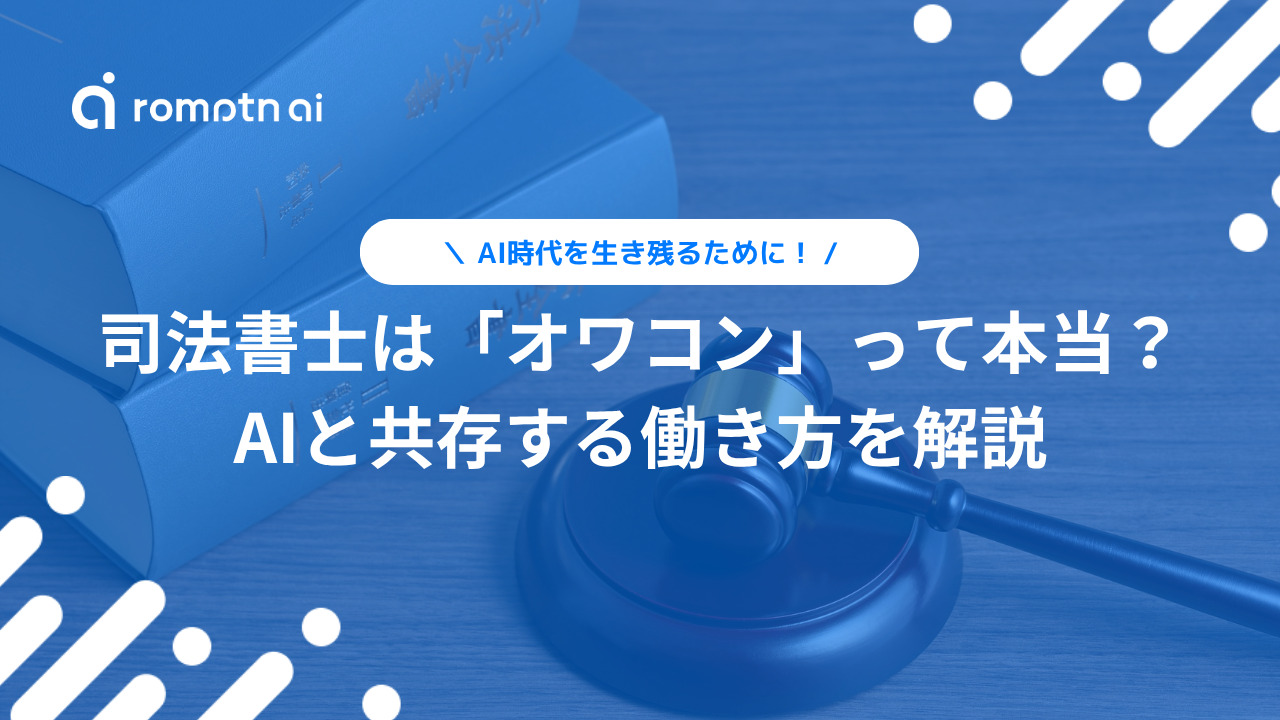AIの進化が目覚ましい昨今では、多くの仕事がAIに代替されつつあります。司法書士の仕事も例外ではありません。実際に司法書士の仕事も一部はAIによる自動化が進んでいます。
ときには、「司法書士はもうオワコンの仕事」といわれてしまうことも。相続や会社設立などの重大なイベントを、司法の観点からサポートする司法書士。そんな司法書士の仕事は、本当にオワコンなのでしょうか?
今回は、司法書士が「オワコン」といわれる理由や、AI時代に生き残るために必要な能力をご紹介します。司法書士に求められる働き方の変化を学び、AIと協働するためのヒントを探していきましょう。
📖この記事のポイント
- 司法書士はオワコンではない。しかしAI技術によって一部業務が代替されつつある
- 少子高齢化により、数十年後にはメイン顧客である高齢者が減少し、競争が激化するリスクがある
- AIツールを活用することで業務が効率化され、より時代に沿った柔軟な働き方を実現しやすくなる
- 司法書士の学習と並行してAIを学ぶためには、セミナーの活用が効果的
- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!
- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!
\ 累計受講者10万人突破 /
無料特典を今すぐ受け取る司法書士が「オワコン」といわれる3つの理由
ここでは、司法書士が「オワコン」といわれる理由を3つご紹介します。社会的に信用を得やすく、将来性も担保されている印象の司法書士。そんな司法書士が、なぜ時代遅れの職業のようなイメージを持たれてしまうのでしょうか?
①AIによる業務自動化の可能性
司法書士が「オワコン」といわれる理由として、AIによる業務自動化が挙げられます。司法書士の仕事のなかには、不動産登記や商業登記のようないわゆる「定型業務」も多く存在しています。定型業務における定例文の作成やデータ処理などの作業は、AIの得意領域です。
AIは定型業務以外にも、相談業務や書類の下書きなども部分的に担えるようになってきています。一部のクラウド登記サービスでは、AIの質問に答えるだけで書類作成まで完結できるほどです。
AIによって、ミスの少ない自動入力やチェック機能が強化されつつある昨今では、士業の「付加価値」が薄れることが懸念されています。
②少子高齢化による市場規模の変化
少子高齢化による市場規模の変化も、司法書士が「オワコン」といわれやすい理由です。たとえば相続や登記などの需要は、若者よりも高齢者が中心。少子化が進む令和の現在、長期的な視点では依頼数が減少すると考えられます。
また不景気が続くなか、若年層のライフスタイルにも変化が現れています。昔と比べて住宅購入数が減少傾向にあるため、不動産登記件数自体も減少傾向にあるのです。その結果、司法書士への依頼数も減りつつあります。
さらに法人設立数も、人口減少の影響で鈍化の傾向に。商業登記の案件が伸び悩み、司法書士の仕事の絶対数自体が減っているのが現状です。地方ではとくに高齢化が深刻。顧客層自体が減ることで、事務所維持が困難になるケースも出てきています。
③法改正や制度変更の影響
司法書士がオワコン化する背景には、法改正や制度変更の影響も存在しています。例として挙げられるのが、相続登記の義務化や手続きのオンライン化です。司法の知識を持たない一般人でも自力で対応しやすくなりつつあるため、司法書士の属人的な仕事が減少傾向にあります。
そもそも法務省がオンライン申請を推進しているので、司法書士の「申請代行」の役割が縮小されつつあるのは事実。さらに今後は登記制度の簡素化が進むことが予想されており、司法書士が手数料収入を確保しにくくなるとも考えられています。
AI時代における司法書士の将来性と仕事の変化
ここでは、AI時代における司法書士の将来性や、変化する仕事の形についてご紹介します。AI技術が躍進し続ける現代において、人間とAIとの協働は避けられないでしょう。AIと競い合うのではなく、AIを道具として扱うことで、司法書士の可能性はさらに広がっていきます。
「AIに代替される可能性が高い業務」とは?
前項でも触れたように、司法書士の業務のなかでも「定型業務」はAIに代わられやすいと考えられます。
不動産登記や商業登記の書類作成をはじめ、定型的な書式・手順でおこなう作業は、自動化の対象に。感情や定性的要素が入らない業務は、ミスが少なく処理の早いAIに任せたほうが効率的といえるでしょう。
実際に一部のサービスでは、名義変更や会社設立に関わる書類作成の補助などは、すでにオンライン上で自動化されています。書類の文言チェックや形式確認はAIに任せやすく、人的確認の必要性が減少しつつあるのです。簡易なアドバイスであれば、チャットボットでも対応可能です。
司法書士業務は、AIによって効率化されていく
定型以外の業務も、AIによって効率化されつつあります。
たとえば、過去案件のデータを活用した業務管理やスケジュール調整などは、AIのサポートを受けることでより快適かつ正確に。またチェックツールや書類の自動生成などのAI化では、確認作業の負担も大幅に減少します。AIが定型的な質問対応を担当することで、司法書士はより専門性の高い対応に集中できるようになります。
司法書士の業務におけるAI化の影響は、単純な「仕事を奪われる」だけではありません。人とAIの作業を適切に住み分けることにより、司法書士の個人としてのレベルが向上することにもつながるのです。
AIと共存する「司法書士の新たな役割」
AI時代における司法書士には、AIでは処理できない問題を紐解き解決する力が求められます。たとえば「複雑な権利関係」や「感情をともなう相続問題」などは、人間的な判断が必要です。
顧客の不安や価値観に寄り添いつつ、法的に最適な手続きにつなげていく提案は、人間にしかできない業務です。今後の時代の変化によっては、ほかの士業との連携や地域包括支援なども、司法書士の業務に関連する可能性があります。
司法書士が「地域の法律インフラ」として貢献する未来も考えられるでしょう。AIツールの導入支援や活用アドバイスができれば、ほかの事業者や士業における「法務×ITコンサル」としての立場も担えます。
AI時代で生き残る司法書士に求められる3つの能力
ここでは、AI時代で生き残るために、司法書士が獲得するべき3つの能力をご紹介します。技術が変われば社会が変わり、市場のニーズが変わり、働く側に求められる能力も変わるもの。時代の変化に柔軟に対応するためにも、今から備えるべき要素を把握しましょう。
①AIでは代替できない「人間力」
AI時代に司法書士が生き延びるためには、AIには代替できない「人間力」が求められます。以下に、司法書士に求められる人間力の例を記載します。
- 「共感力」……相続時やトラブル時の相談など、感情や価値観に配慮するための力
- 「傾聴力」「提案力」……顧客が本当に望む手続きや、言葉の裏に隠された本心を引き出し、提案する力
- 「信頼関係の構築力」……緊張や不安を感じる顧客に安心感を与える力
- 「バランス感覚」「論理的判断力」……複数の選択肢から最適解を導く力(AIが苦手とする領域)。
とくに信頼関係の構築は、まさに人間にしかできない仕事。顧客に「この人になら任せられる」という付加価値を与えることで、人的な価値が高まっていきます。
②専門性を超えた「複合的な知識」
AIとの効果的な協働のためには、専門性を越えた「複合的な知識」も求められます。なぜならAIは、複数の領域の横断的な嗜好が苦手な傾向にあるからです。たとえば税務・副詞・心理などの異なる分野の知識を持つことで、より実践的かつ柔軟な法的支援が実現します。
とくに相続や事業の継承などに関連する業務では、家族関係や経営戦略の視点を踏まえた「総合的な助言力」が必要に。人間関係や感情面に配慮した提案は、やはりAIには難しいものです。
ほかにも不動産や金融、ITなどの分野への理解は、依頼者との信頼構築や幅広いニーズへの対応につながります。
③変化に対応できる「学習能力と柔軟性」
AI時代に対応する司法書士になるためには、変化に対応するための「学習能力と柔軟性」も必要です。AIとの協働は避けられない未来だからこそ、AIツールを業務改善に活かすための「ITリテラシーの高さ」は、競合との大きな差につながります。
また何かと変化が多い現代では、法改正や社会制度の変更に敏感に反応し、対応策をすぐに取り入れる柔軟性も重要です。ニーズの変化に合わせて自らの業務領域を再定義し続ける「自己変革力」が、AI時代の大きな武器になるでしょう。
AI時代で生き残るためには、一つの働き方に固執しない姿勢が求められます。「司法書士はこうあるべき」という固定観念を捨て、社会や技術の変化に合わせ、業態やサービスの内容なども柔軟に変更していきましょう。
今からでも司法書士を目指すべき?判断ポイントと注意点
ここでは今から司法書士を目指す人のために、ポイントや注意点をご紹介します。司法書士は、国内最高峰レベルの難関資格。実際に資格を取得するまでの間に、社会の有り様も変化していることが考えられます。予測される未来から逆算しつつ、専門知識以外にも備えるべき要素を把握していきましょう。
司法書士資格取得の難易度と期間
今から司法書士を目指す際は、まず「司法書士資格を取得する予定時期」を定めます。司法書士の合格率は例年4~5%と非常に低い傾向に。法律系国家資格のなかでも、トップクラスの難関です。
初めての受験でゼロから学び始める場合は、合格までに必要な勉強時間は平均で3,000〜4,000時間ともいわれています。多くの受験生は、合格までに2~3年の期間が必要です。
対してAI技術の界隈は、最新情報も半年程度で時代遅れになるほどスピーディー。資格を取得する頃にAIの技術がどれほど進化しているかは未知数です。
そのため「現在のAIとの協働の形」と「数年後の協働の形」には、大きなギャップが生じている可能性があります。資格取得の困難さを加味したうえで、時代の変化とともに働き方のイメージを一新していく姿勢が必要です。
AI時代に対応した学習方法
今から司法書士を目指す人は、将来的なAIとの協働を予測し、AI時代に対応した学習方法を実行しましょう。
とはいえ「司法書士の勉強」と「AI時代を学ぶための勉強」は、別の領域です。専門知識を繰り返し学ぶ最中に、AIに関する最新情報をキャッチアップする環境を保持する必要があります。また時期や制度の改正などにより、実務への応用のスタイルが変わるリスクも存在しています。
そこで取り入れたいのが「司法書士の勉強にAI技術を取り入れる」という方法です。
たとえば「AIに試験問題を作ってもらう」「学習用のポッドキャストを作ってもらう」「学習書籍を読み込ませて要約を作ってもらう」などの方法が挙げられます。
日常的な学習のなかに無理なくAI技術を導入することで、トレンド察知能力を磨きつつ、AIリテラシーを高められます。何より、「資格取得時にAIに関する基礎的な知識がある」という事実は、司法書士としての未来を豊かにするための協力なサポートになるでしょう。
司法書士として働くうえでの具体的な展望
司法書士として働き続けるためには、社会の変化を汲む姿勢が求められます。
たとえば相続・遺言・家族信託など、高齢化社会との関連が深い業務は、今後も一定の需要が見込まれるでしょう。
しかし司法書士のメインの顧客が高齢者である限り、少子高齢化の影響を受け、何十年か後には案件数が激減してしまうリスクがあります。
市場競争が激化する未来で生き残るためには、業務効率と信頼性の両立が重要です。そこで鍵となるのが、ITツールやAIツールの活用です。
AIを使いこなせる司法書士は、同じ労働力でも生産性が上がり、サービス単価を下げられるようになります。かつ定型業務をAIに依頼できるため、自身は専門性や非認知能力を高める学習に尽力できるのです。
分野横断的な専門性を獲得できれば、将来的には相談業務や地域連携を重視した「法務×福祉」「法務×教育」などの展開も可能になります。
司法書士はオワコンではない!AIを味方にする働き方が大切
今回は、司法書士が「オワコン」といわれる理由や、AIとの協働の形についてご紹介しました。
結論から言うと、司法書士はオワコンではありません。案件は高齢者を中心に安定しており、AIでは捌けない非定型業務も多く存在しています。
しかし数十年後にはメイン顧客数の減少により、市場の競争が激化すると予想されます。競合と差をつけるために獲得したいのが、AIに関するスキルや知識です。
司法書士としてより柔軟性のある働き方を実現するために、日常業務や学習過程にAIツールを取り入れ、リテラシーを高める取り組みを始めていきましょう。
romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。
AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。
AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。
\累計受講者10万人突破/