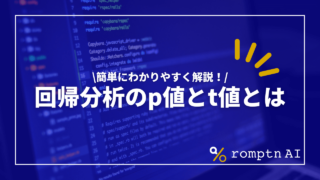 AI用語
AI用語 回帰分析のp値とt値を理解する|有意性の正しい見方と使い方
回帰分析のp値とt値の意味・違い・見方をやさしく解説。p値が小さいときの解釈や有意性の考え方も、実例付きでわかりやすく学べます。
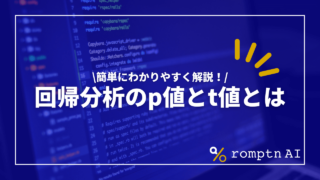 AI用語
AI用語  AI用語
AI用語 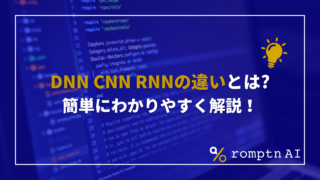 AI用語
AI用語 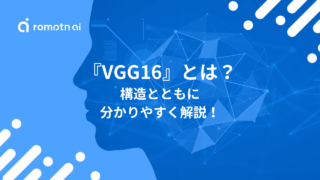 AI用語
AI用語 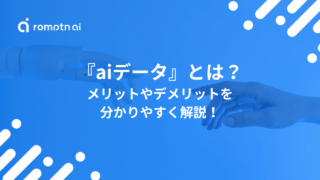 AI用語
AI用語  AI用語
AI用語 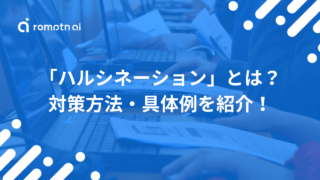 AI用語
AI用語