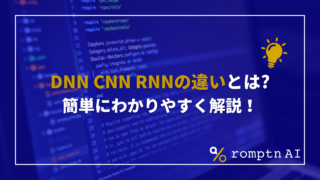 AI用語
AI用語 DNN CNN RNNの違いとは|簡単にわかりやすく解説
DNN・CNN・RNNの仕組みと違いを図と表でわかりやすく解説。画像・文章・時系列など、データの種類に応じたモデルの選び方と使い分けを初心者にも理解しやすく整理します。
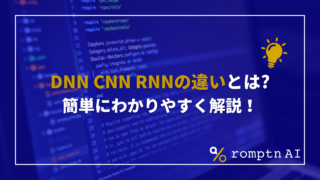 AI用語
AI用語 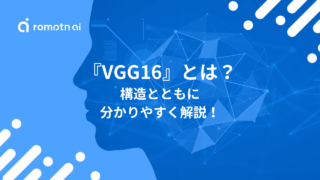 AI用語
AI用語 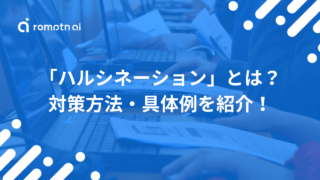 AI用語
AI用語  AI用語
AI用語 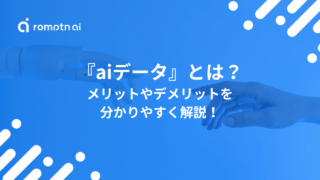 AI用語
AI用語 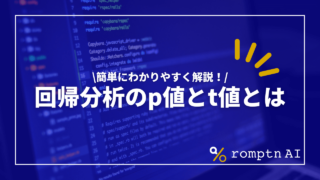 AI用語
AI用語  AI用語
AI用語