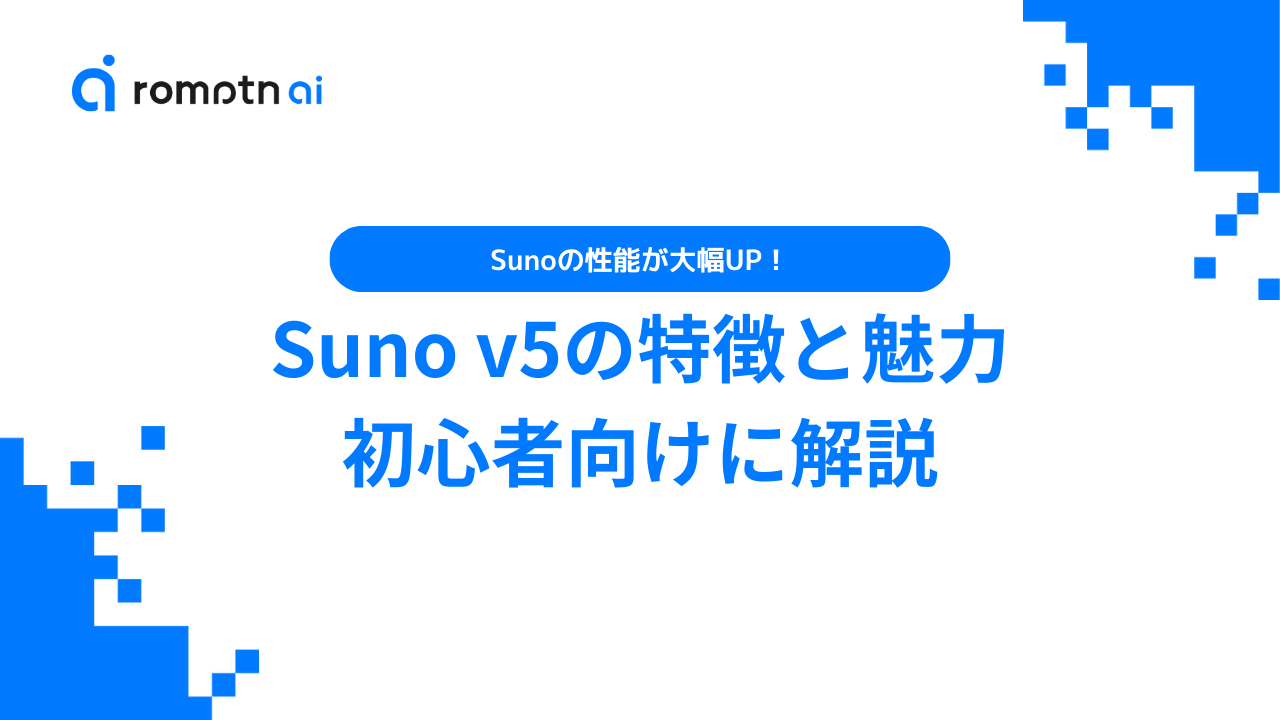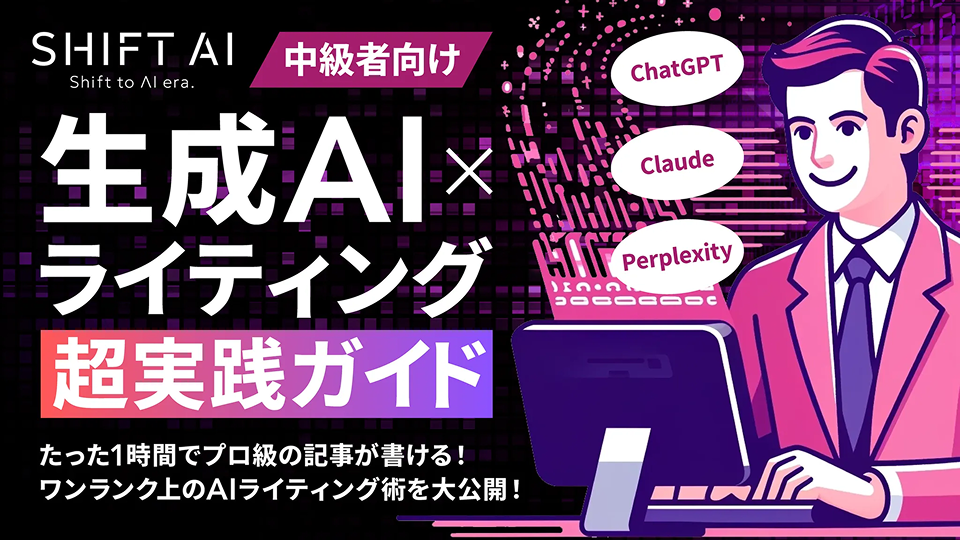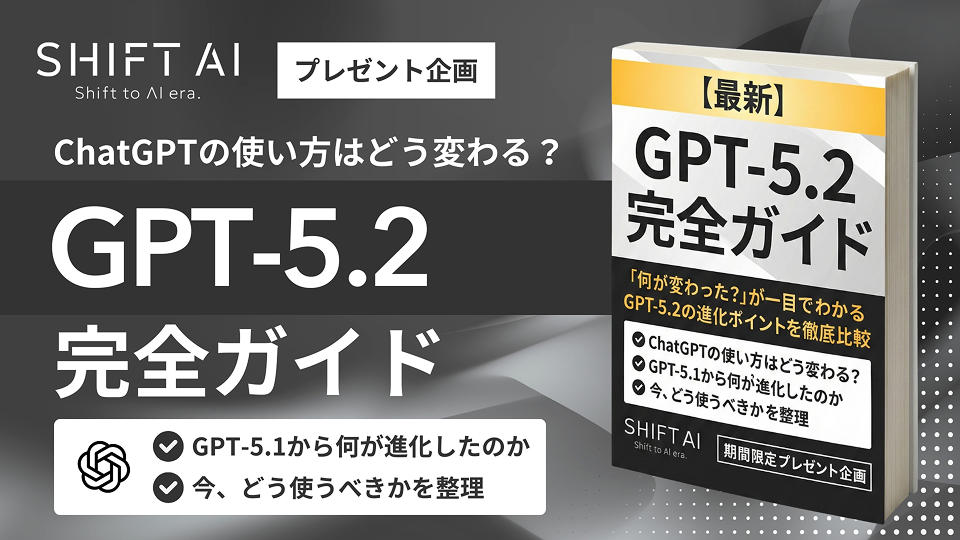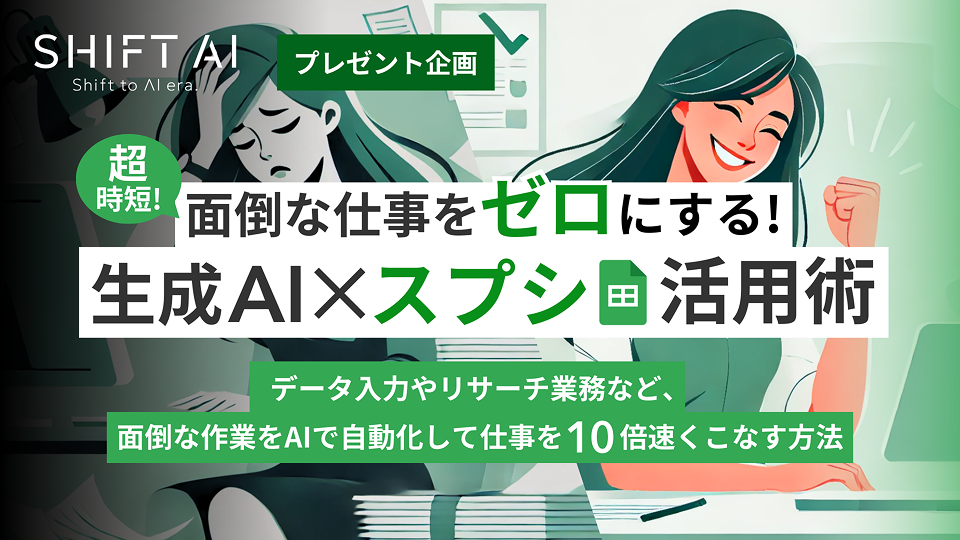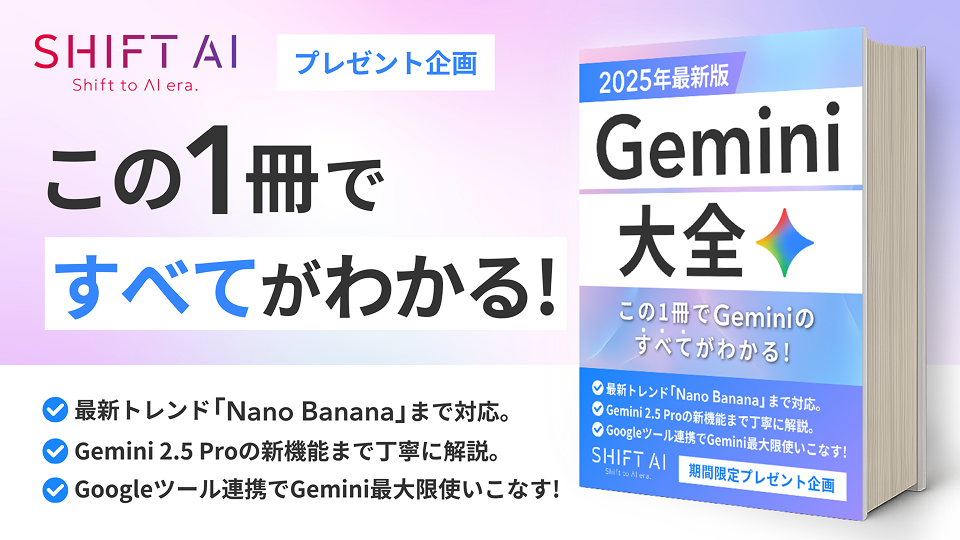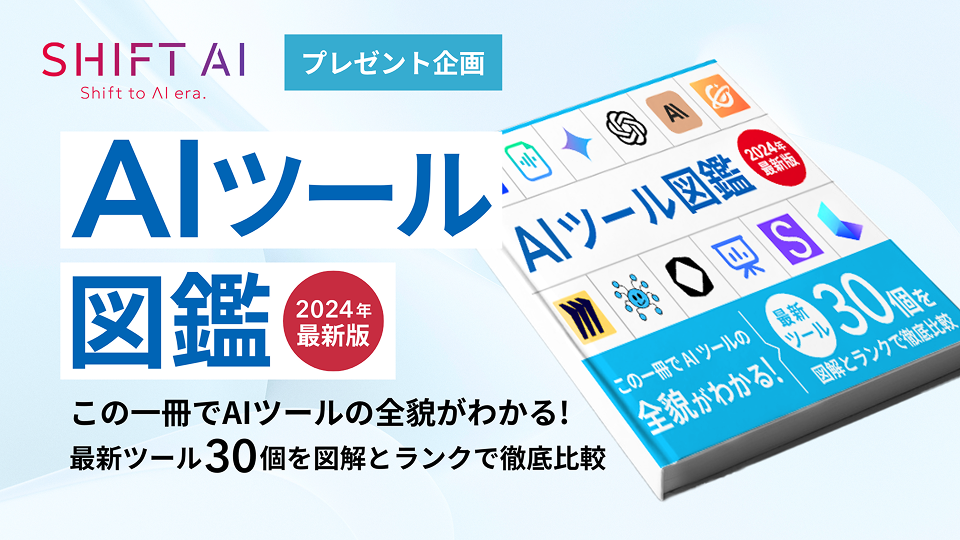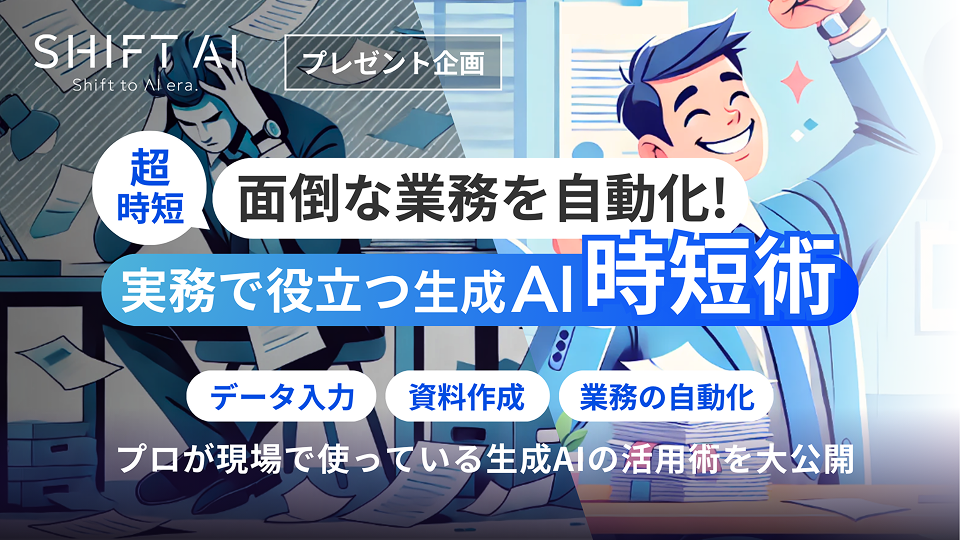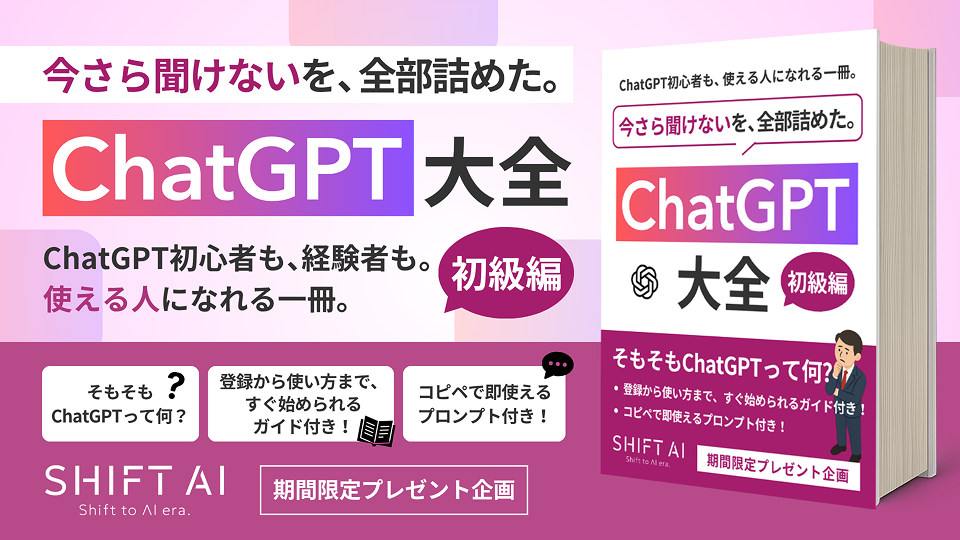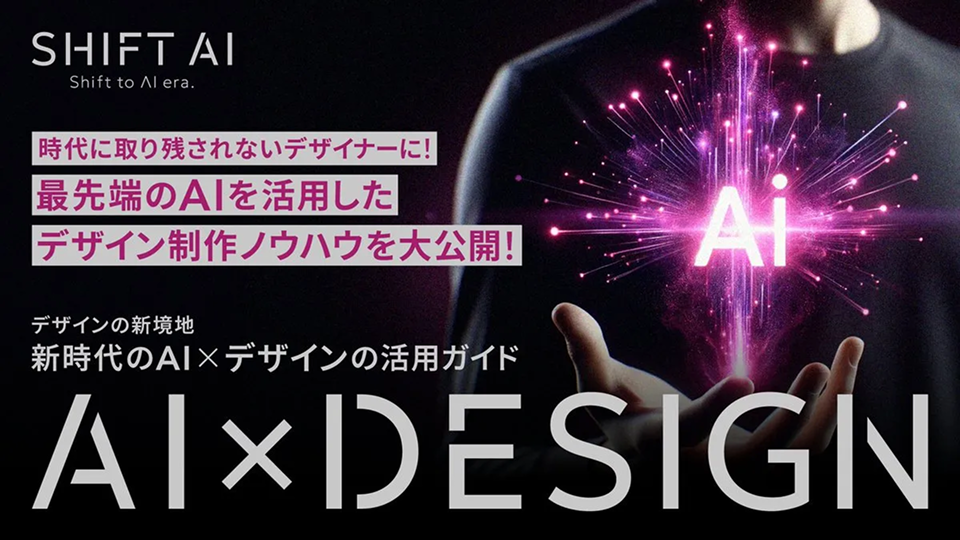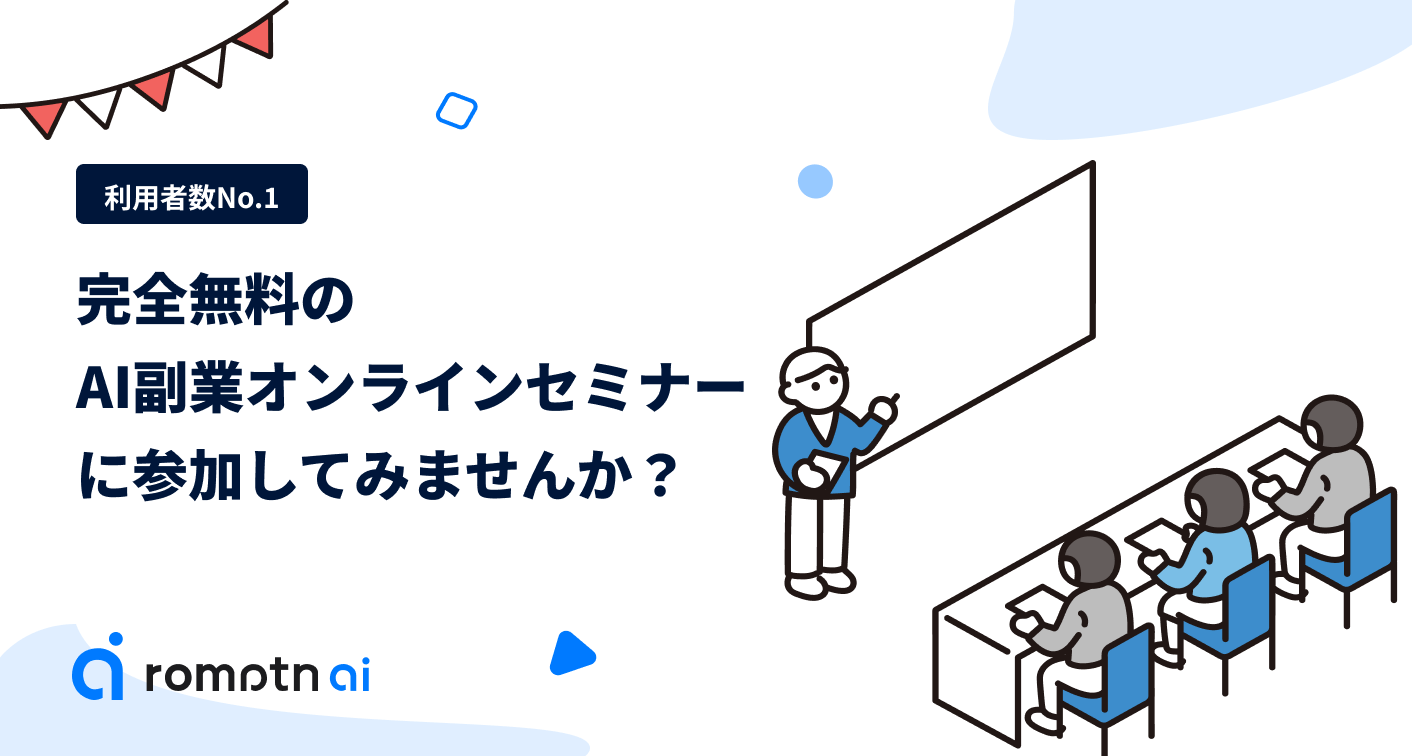最近、生成AIによるMV制作などで、SNSやYouTubeで話題を集めている「Suno」。AIが歌やメロディを自動で生み出してくれる音楽生成ツールです。
その最新バージョンが「Suno v5」。従来よりも自然な歌声や一貫性のある構成、スピーディな生成が可能になり、初心者でも驚くほど簡単に本格的な曲づくりを体験できるようになりました。
本記事では、Suno v5の特徴や使い方、さらにプロンプト作成のコツまで、わかりやすく徹底解説していきます。
内容をまとめると…
Suno v5は最新のAI音楽生成モデルで、自然な歌声や一貫性のある楽曲構成を誰でも簡単に体験できる!
テンポ・キー・アレンジを細かくコントロール可能で、最長8分の楽曲も破綻なく生成できる。
無料プランは非商用、有料プランは商用利用OKで、WAV形式のダウンロードや高度な編集が可能。
Suno Studioとの連携で、マルチトラック編集やMIDIエクスポートなどプロ向けの制作環境にも対応
最新の生成AI情報をキャッチアップして、実際に活用できるスキルを身に付けたいなら、まずは無料で生成AIのプロに教わるのが近道!
豪華大量特典無料配布中!
romptn aiが提携する完全無料のAI副業セミナーでは収入UPを目指すための生成AI活用スキルを学ぶことができます。
ただ知識を深めるだけでなく、実際にAIを活用して稼いでいる人から、しっかりと収入に直結させるためのAIスキルを学ぶことができます。
現在、20万人以上の人が収入UPを目指すための実践的な生成AI活用スキルを身に付けて、100万円以上の収益を達成している人も続出しています。
\ 期間限定の無料豪華申込特典付き! /
AI副業セミナーをみてみる
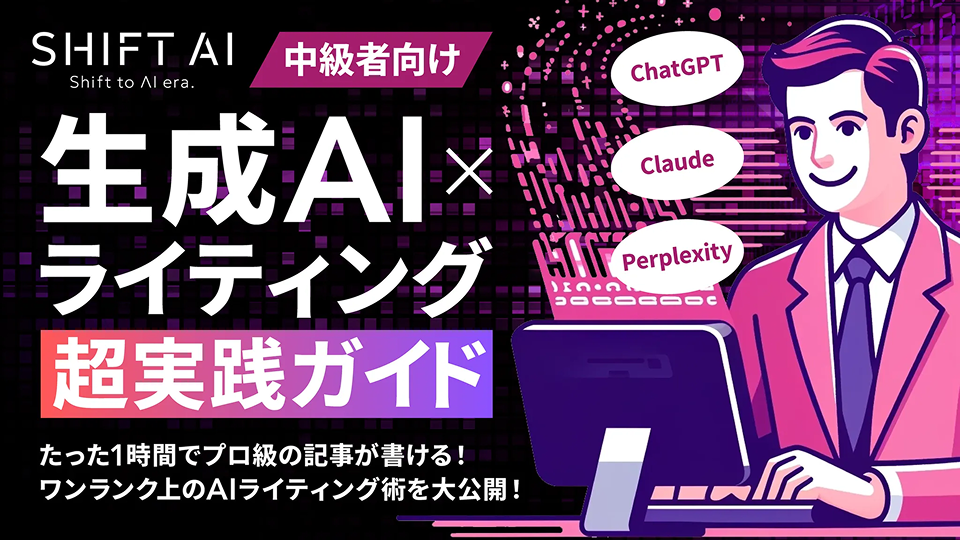
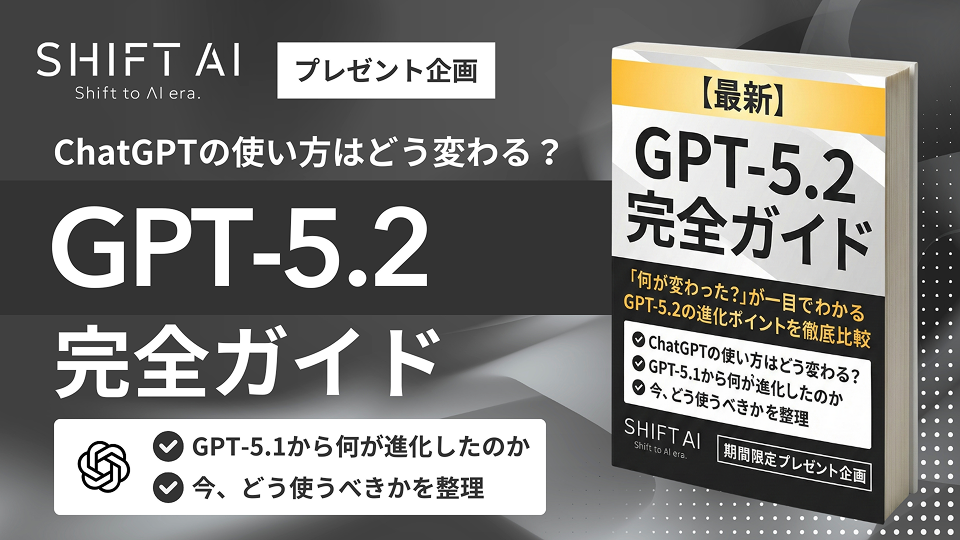

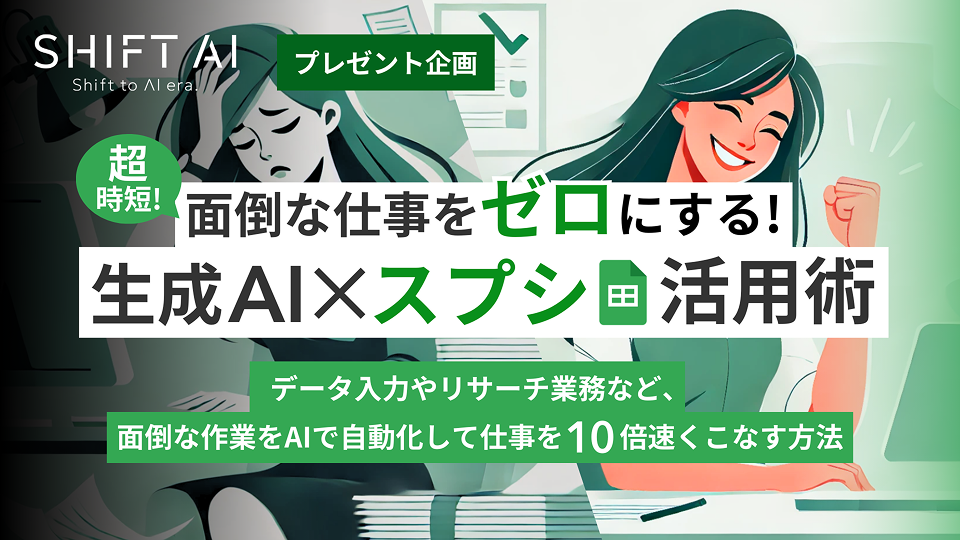
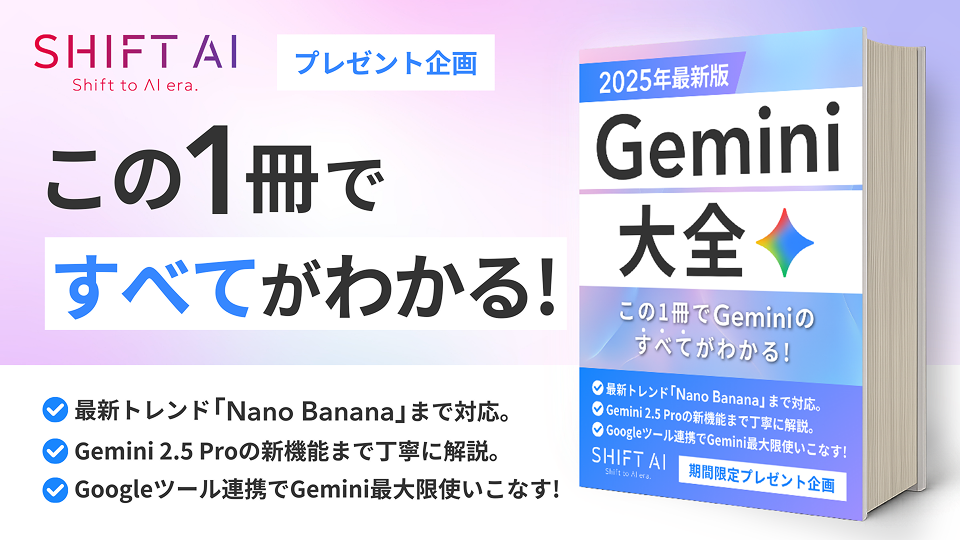
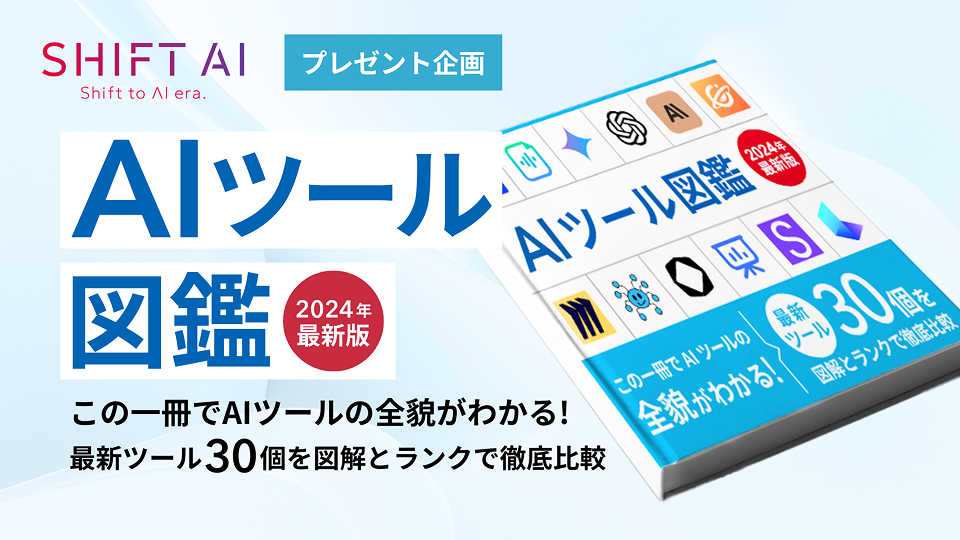
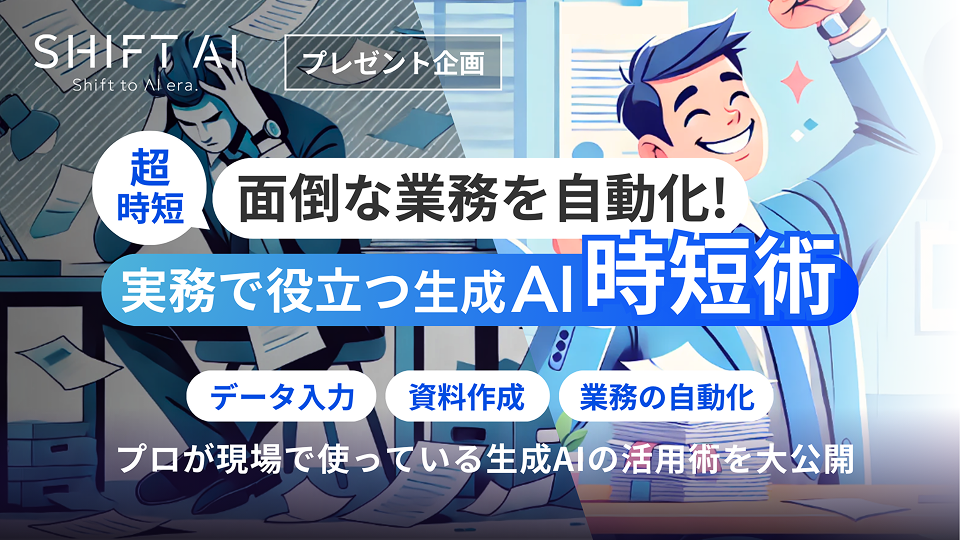

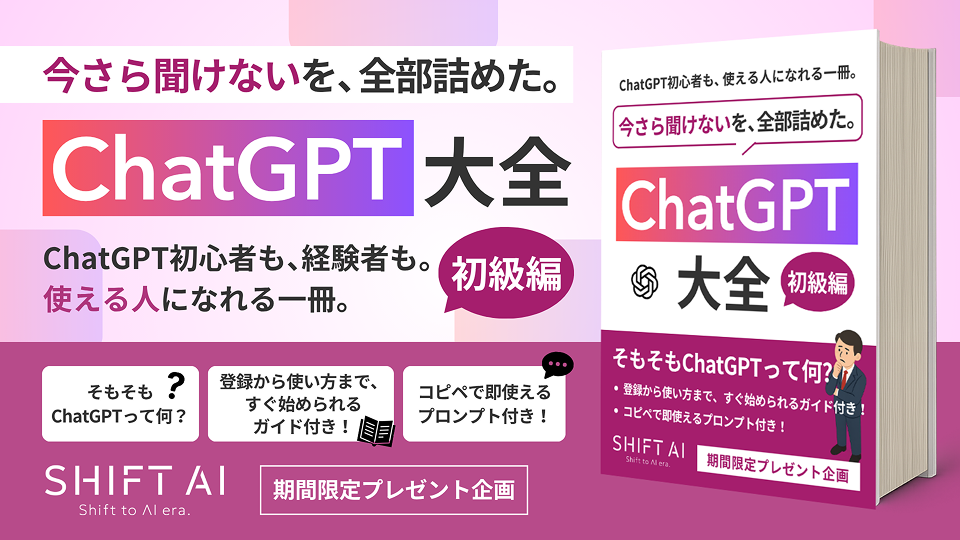
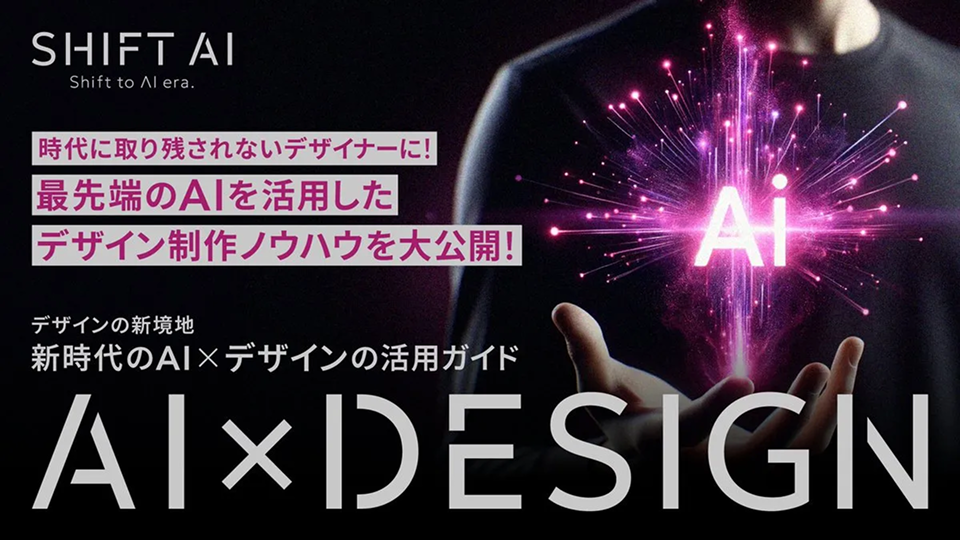

Suno v5とは?
AIを使って音楽を自動で作れるサービス「Suno」。その最新バージョンが「Suno v5」です。
これまで以上に自然な歌声や一貫性のある構成が実現され、初心者でも驚くほど手軽に本格的な楽曲制作が楽しめるようになりました。
ここでは、Suno v5がどんなモデルなのか、利用条件や新しく登場した「Suno Studio」とあわせて紹介していきます。
- Suno v5の基本概要
- Suno v5の利用条件
- Suno Studioの基本概要
Suno v5の基本概要
Suno v5は、AIを活用してメロディや歌詞を自動生成する最新モデルです。短いフレーズから8分近いフル楽曲まで、スムーズな展開を持った曲を生み出せるのが大きな特徴です。
歌声の自然さや演奏のまとまりが強化されており、まるで人間のミュージシャンが演奏したかのような仕上がりになります。
Suno v5の利用条件
リリース直後は、Suno v5は有料プラン(ProまたはPremier)のユーザーが利用可能です。無料プランでは引き続きSunoを試せますが、最新のv5モデルは対象外となっています。
有料プランなら作成した曲を商用利用することもでき、SNS投稿や音楽配信にも活用できます。
Suno Studioも登場!
さらに、Suno v5と同時に「Suno Studio」という新しい編集ツールも発表されました。これはAIが作った曲を、より自由に調整できる専用のワークスペースです。
- ボーカルやドラムなどを別々のトラックに分けて編集できる
- MIDI形式で書き出して、他の音楽ソフトに持ち込める
- 初心者でも扱いやすいシンプルな操作画面
これにより、「AIが作った曲をそのまま使う」だけでなく、「自分好みに仕上げる」という新しい楽しみ方が可能になっています。
Suno v5の主な進化
Suno v5は、これまでのバージョン(v4、v4.5)から大きく進化しています。単なる音質の向上にとどまらず、長尺の楽曲構成や細かいコントロール性、歌声のリアリティまで大幅に改善されました。ここでは、Sunoの公式の発表情報をもとに、その代表的な下記の主な5つの進化ポイントを詳しく見ていきましょう。
- 構成の一貫性
- コントロール性
- ボイス/楽器の継続性
- ボーカルの自然な表現力
- 生成スピードの大幅UP
①構成の一貫性
従来のAI音楽生成では、1曲を通して聴いたときに「サビだけ良いけど、AメロやBメロがつながらない」といった不自然さが課題でした。
Suno v5では、30秒の短いフレーズから8分近い長編楽曲まで、イントロ・Aメロ・サビ・アウトロといった流れが自然につながるように設計されています。
そのため、BGMや配信用のフル楽曲でも破綻せずに使えるのが大きな魅力です。
②コントロール性
Suno v5では、テンポ(BPM)、キー(調)、ダイナミクス(強弱)、アレンジ(楽器構成)を細かく指定できるようになりました。
たとえば「120 BPMの爽やかなシティポップ」「キーをDマイナーにして切なさを演出」といった音楽的な要望をAIに反映できます。これにより、単なる自動生成ツールから「自分の意図を反映できる制作パートナー」へと進化しています。
③ボイス/楽器の継続性
以前のバージョンでは、曲の途中でボーカルの声質が変わったり、ギターやドラムの音色が突然変化するケースがありました。
v5ではこの点が大きく改善され、同じ人物が歌い続けているかのような安定感が出ています。
さらに、リード楽器やベースラインのキャラクターも一貫して維持されるため、曲全体の完成度が一段と高まりました。
④ボーカルの自然な表現力
Suno v5では、特にボーカル表現のリアルさが際立ちます。息づかいや抑揚、フレーズの切り方まで自然に再現されるため、単なる「ロボットの歌」から「人間のシンガーの歌声」に近づいています。
たとえばポップスでは感情を込めたサビ、バラードではしっとりとした抑揚を持たせるなど、ジャンルに応じたニュアンス表現も可能になりました。
⑤生成スピードの大幅UP
音質や表現力だけでなく、生成スピードも大きく向上しました。公式の発表では、従来の最大10倍の速さで曲が仕上がるとされており、思いついたアイデアをすぐに音として確認できます。
これにより、クリエイターは試行錯誤のサイクルを短縮でき、より多くの楽曲を効率的に制作できるようになりました。
v4・v4.5・v5の比較
| 項目 | v4 | v4.5 | v5 |
| 主な特徴 | 基本的なメロディ生成に対応。短尺での利用が中心。 | 音のバランスやノイズを改善。長尺でも破綻しにくい。 | 構成の一貫性・コントロール性・歌声のリアリティが大幅進化。 |
| 曲の長さ | 最大4分程度 | 最大8分 | 30秒~8分まで高品質 |
| ボーカル・楽曲表現 | ボーカルはやや機械的 | 自然さが増し、安定感が向上 | 声や楽器のキャラクターが持続、感情表現も自然 |
| 生成スピード | 3~5分程度 | v4より高速 | 最大10倍の高速化 |
| 利用条件 | 無料・有料問わず利用可 | 無料・有料で利用可(制限あり) | 有料プラン(Pro・Premier)のみ利用可 |
Suno v5 の始め方
Suno v5は、専門的な知識がなくても直感的に扱えるのが大きな魅力です。ここでは、初めて触れる方でもスムーズに楽曲を作れるように、基本的な流れを解説します。
STEP①歌詞やアイデアを入力する
画面にある「Lyrics(歌詞)」の欄に、自分がイメージする歌詞やフレーズを入力するだけでAIが自動的にメロディをつけてくれます。
歌詞がなくても「元気なポップソング」「しっとりとしたピアノバラード」といったキーワードを入力するだけで、それに合った曲を作ってくれます。
STEP②スタイルやジャンルを選ぶ
次に「Style」の欄で曲の方向性を指定します。たとえば「city pop」「EDM」「lo-fi hip hop」などのジャンルや、「80年代風」「映画音楽のように壮大」といったムードを加えると、完成する楽曲の雰囲気がぐっと理想に近づきます。
ポイントは、できるだけ具体的な言葉を使うことです。「楽しい」「明るい」だけでなく、「夏の夜に聴きたくなるような」「雨の日に似合う切なさ」といった表現を足すと、AIがより的確に解釈してくれます。
STEP③Remasterやステム編集で仕上げる方法
曲が生成されたら、そのままでも十分なクオリティではありますが、より本格的に仕上げたい場合は「Remaster」や「ステム編集」を活用しましょう。
- Remaster:音のバランスを整えたり、明瞭さを強めたりすることができます。軽い調整から大幅なアレンジまで選べるので便利です。
- ステム編集:ボーカル、ドラム、ギターなどを個別のトラックに分解できます。これにより、ボーカルだけを取り出してリミックスしたり、ドラムを差し替えたりといった高度な編集が可能になります。
これらを組み合わせれば、初心者でもオリジナル曲を磨き上げ、YouTubeやSNSに投稿できるような完成度に仕上げることができます。
Suno v5プロンプト作成のTIPS
上記では基本的な楽曲生成手順を紹介しましたが、Suno v5でより理想的な楽曲を作るためには、入力する「プロンプト(指示文)」の工夫が欠かせません。同じ言葉でも書き方次第で仕上がりが大きく変わるため、生成AIツールの使用に慣れている方は下記のいくつかのコツを押さえておきましょう。
- 英語で書くのが基本中の基本
Sunoの内部は英語ベースで学習されているため、プロンプトも英語で書くのがおすすめです。日本語でもある程度は動作しますが、細かなニュアンスや音楽ジャンルの解釈は英語の方が安定します。Suno自体が英語話者であるという前提の意識を持つことが重要です。 - 重要なワードを冒頭と末尾に置く
「city pop」「EDM」「acoustic ballad」などのジャンル名やスタイルは、プロンプトの冒頭と末尾に入れるとAIが強く解釈してくれます。これにより、楽曲の方向性がぶれにくくなります。 - 歌詞やストーリーに動きをつける
ただの情景描写よりも「夏の夜、都会の光を抜けて踊る」といった動的な描写を入れると、リズムやメロディに勢いが出やすくなります。プロンプトは単なる設定ではなく、音楽の設計図としての役割を意識しましょう。 - ムードや感情を具体的に伝える
「悲しい」「明るい」だけでなく、「雨の日に聴くと心が落ち着くような」「別れを乗り越える強さを感じる」といった感情表現を入れることで、歌声や演奏にニュアンスが反映されやすくなります。 - JSONorYAML形式など構造化された形式を使う
長いプロンプトを書く場合は、JSONやYAMLのように構造化して書くと整理しやすく、AIにとっても解釈しやすくなります。特に「歌詞」「ジャンル」「楽器構成」「ムード」などを分けて指定すると、安定した仕上がりが得られます。 - プロンプト作成はChatGPTやGeminiなどを活用する
「自分ではうまくプロンプトを書けない」と感じたら、ChatGPTなど他のAIで歌詞や雰囲気を下書きしてからSunoに流し込むのも有効です。 - 感情表現の指示を優先する
「悲しみを込めた歌声」「力強いコーラス」といった表現は、楽曲全体の印象を左右します。曲調やジャンル指定と合わせて感情キューのような抽象的な指示を加える方が、一層自然な仕上がりになります。 - Creative Boostは控えめに
Sunoには「Creative Boost」というオプションがありますが、これを強く効かせすぎると予想外のアレンジが入りすぎることも。まずは控えめに使い、必要に応じて調整するのがコツです。 - 日本語では発音や歌詞の工夫が必要
日本語歌詞をそのまま入れると発音が不自然になることがあります。英語のルビを併記したり、簡単なフレーズにすることで、より自然な歌声に近づきます。
Suno V5の活用シーン
Suno v5は「ただの自動作曲ツール」ではなく、アイデア次第で幅広い場面に応用できます。ここでは実際に役立つ利用シーンをいくつかご紹介します。
- YouTubeやSNSのBGM作成
- ゲームや動画の効果音
- オリジナル楽曲制作・配信
YouTubeやSNSのBGM作成
YouTube動画やInstagramリール、TikTokのショート動画に「オリジナルBGM」をつけたいときにSuno v5は大活躍します。既存の楽曲を使うと著作権の制限が気になる場面でも、自分で生成した音楽なら安心です。
しかも映像の雰囲気に合わせて「明るく元気なポップ」「落ち着いたLo-fi」といった指示を出すだけで、世界観にぴったりの楽曲が作れます。
ゲームや動画の効果音
ゲーム制作や映像編集では、シーンごとに短いBGMや効果音が必要になります。Suno v5なら「緊張感のあるバトル曲」「やさしいピアノのメロディ」といった要望をその場で反映でき、既存の素材集に頼らずオリジナルのサウンドを揃えることができます。個人制作のクリエイターにとって、大きな武器になるはずです。
オリジナル楽曲制作・配信
「シンガーソングライターのように自分の曲を世の中に出したい」と思っても、作曲やアレンジのハードルが高いと感じる人は少なくありません。Sunoを使えば、ある程度のイメージをまず形にしたり、楽曲制作の始めの一歩のハードルがとても低くなります。
そして、歌詞やイメージを入力するだけで完成度の高い楽曲が作れるため、初心者でもオリジナル曲を配信できます。有料プランであれば商用利用も可能なので、ストリーミングサービスや音楽販売に載せることも可能です。
【参考】音楽生成AIに関する音楽業界の動向・リスク
AIで音楽を自動生成する技術は急速に発展しており、それをめぐる業界の議論や法制度の変化も激しくなっています。Suno v5を使ううえで、知っておきたい最新の動向とリスクを整理しておきましょう。
著作権と法制度の不確実性
アメリカの著作権法では、「人間の創作性」があるものだけが保護対象とされる傾向があり、完全にAIだけで生成された音楽は著作権保護を受けにくいという見解が存在します。Suno が「Pro / Premier で作った曲はユーザーが所有する」としていても、法制度上の保護が認められない可能性が残ります。
Suno は AI モデルの訓練に際して大量の音楽を用いたという主張・訴訟も起きています。RIAA(アメリカの大手音楽レーベル団体)は、Suno に対して「YouTube から無断で楽曲を取得してモデル学習に使った」として訴訟を提起しました。
また、小規模アーティストからも訴えが出ています。「SunoのAIが著作権で保護された独立アーティストの楽曲を無断で学習し、類似楽曲を生成した」として賠償を求める訴訟が起こされています。
ただし、AI生成ツールを使う際に「訓練データからそのままコピー」するのではなく、音楽的パターンや特徴を抽象化して生成するタイプのモデルもあり、著作権侵害にならないと主張する専門家もいます。
アーティスト・音楽産業への影響
音楽業界では、AI生成楽曲が増えることによって「オリジナル楽曲の価値低下」「ストリーミング報酬の希薄化」など懸念があります。AI生成曲が大量にアップロードされると、配信プラットフォーム上での競争が激化する可能性があります。
実際に Spotify は AI を使ったスパム楽曲を大量に排除したという報道があります。たとえば、AIによる偽曲(短時間複製・有名アーティストを模したものなど)が報酬を狙って投稿され、それをプラットフォーム側が削除しているという動きがあります。
また、ストリーミングサービス側も AI生成コンテンツに対する対応を強化する動きがあります。たとえば、AI生成であることを明示し、偽装や模倣を防ぐためのルール作りなどが議論されています。
規制・法律対策の動き
一部の州や国では、声のクローン・模倣(ディープフェイク音声)を規制する法律も出始めています。アメリカ・テネシー州では、本人の声を無断でAIで複製することを違法とする「ELVIS Act(Ensuring Likeness Voice and Image Security Act)」という法律が成立しています。
音楽業界と著作権機関は、AIツール開発者と ライセンス契約 を結ぶ動きも始めています。Suno や Udio は大手音楽出版社とのライセンシング交渉を行っており、将来的には訓練データ使用の透明性や権利者配分の仕組みが変わる可能性があります。
利用者が押さえておきたいリスクと対策
ここまでみたきたように、法的観点懸念は多くあり、白黒の範囲が明確ではありません。そのため、下記に挙げるような基礎的な5つの観点は意識して利用することが大切です。
- 模倣・類似性検査:生成された楽曲が既存曲とあまりにも似ていると、著作権侵害のリスクがあります。使用前に類似性チェックを行うと安全性が高まります。
- 証拠の記録:プロンプト入力履歴・生成日時・バージョン情報などを記録しておくと、後から「自分で創った」という主張の補強になります。
- 使用範囲の確認:商用利用が許可されていても、各国の法律やストリーミングサービスの制約をよく確認すること。
- AIツールの利用規約遵守:Suno の利用規約や ToS(使用条件)には、生成物の使用範囲や権利帰属の記載があります。これを遵守して使うことが大前提です。
- 過度な依存を避ける:完全にAIに任せるだけでなく、人間の編集を加えることでオリジナリティを担保し、法的にもクリアな作品をつくるスタンスが望ましいです。
よくある質問
- Q無料プランでも v5 は使えますか?
- A
v5リリース直後は、Suno v5は有料プラン(Pro・Premier)のみで利用できます。また、無料プランでは従来モデルを使えますが、商用利用はできません。
- Qv5 の最大曲長は?
- A
Suno v5では、最短30秒から最長8分までの楽曲を生成可能です。長尺でも構成が自然につながるのが大きな進化ポイントです。
- QWAV で落とせますか?
- A
はい。有料プランではWAV形式でのダウンロードが可能です。無料プランの場合はMP3やM4Aのみとなります。
- QSuno v5にAPIはありますか?
- A
公式の一般公開APIはありません。ネット上で「Suno API」を名乗るサービスは非公式のものが多く、安定性や利用規約上のリスクがあるため注意が必要です。
- Q商用利用はできる?
- A
有料プランで作成した楽曲は商用利用が可能です。YouTubeやSNS投稿、配信サービスへの公開にも対応しています。ただし、国や地域ごとの著作権ルールは異なるため、利用時は各サービスの規約も確認してください。
まとめ
Suno v5は、これまでのAI音楽生成モデルを大きく進化させた最新バージョンです。
- 自然な歌声と一貫性のある構成により、短いフレーズからフル楽曲まで完成度の高い音楽を自動生成。
- テンポやキーなどの細かなコントロールが可能になり、初心者でもプロ並みの表現ができる。
- 有料プランでは商用利用もOKで、YouTubeや配信サービスにも安心して活用できる。
- Suno Studioの登場により、マルチトラック編集やMIDIエクスポートなど本格的な音楽制作にも対応。
AIが生み出す音楽はまだ新しい分野ですが、Suno v5を使えば誰でも気軽に「音楽クリエイター体験」ができます。趣味でBGMを作りたい人から、作品を配信してみたい人まで、幅広いユーザーにとって新しい可能性を開くツールといえます。