 AIツール
AIツール Gensparkで領収書・請求書を取得する方法をわかりやすく解説!
Gensparkの領収書・請求書を取得する手順を、メールとWebサイトでそれぞれのアプローチ方法を詳しく解説!インボイス制度(適格請求書)への対応状況や、名義変更、日本円表記の可否なども解説
 AIツール
AIツール 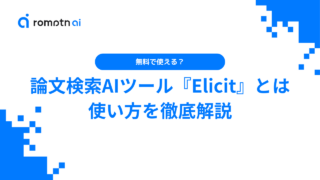 AIツール
AIツール 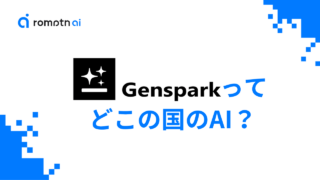 AIツール
AIツール  AIツール
AIツール 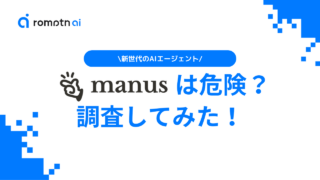 AIツール
AIツール 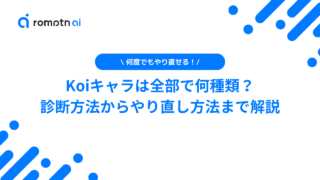 AIツール
AIツール  AIツール
AIツール 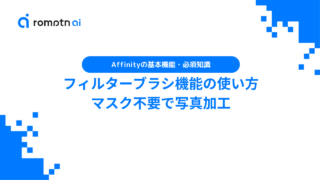 AIツール
AIツール  AIツール
AIツール 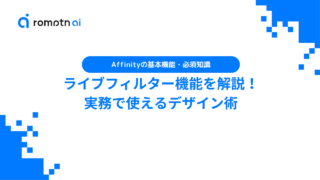 AIツール
AIツール