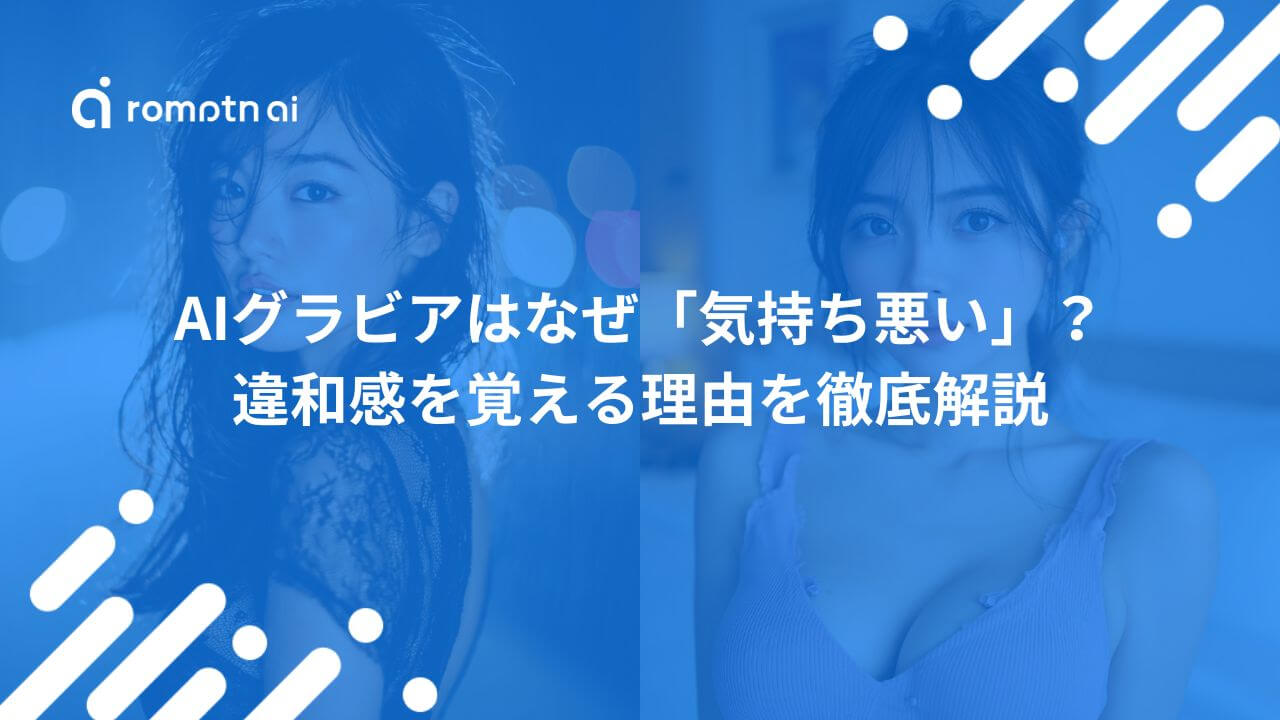最近、SNSや広告でAIが生成したグラビア画像を見かけることが増えましたよね。
実は筆者は最初にAIグラビアを見たとき、「確かに美しいけど、何か違う…」という感覚を覚えたんです。この記事を読んでいる方の中にも、
- AIグラビアを見て違和感や不快感を覚えたことがある
- なぜAIグラビアが「気持ち悪い」と言われるのか理由を知りたい
- AIグラビアの技術的な課題や倫理的な問題点について知りたい
という方がいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、AIグラビアが「気持ち悪い」と感じられる理由について、技術的な側面から心理学的な観点まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説していきます!
📖この記事のポイント
- AIグラビアが「気持ち悪い」と感じられる理由は、不自然な完璧さや個性の欠如、倫理的な問題など複数ある
- 「不気味の谷」現象により、人間に近いけど完全ではないAI画像に違和感を覚える
- AIグラビアの技術は急速に進化しているが、表情や感情の表現にはまだ課題が残っている
- AIグラビアの技術を学べば、収益化のチャンスも!
- SHIFT AIの無料セミナーならAIのプロから無料で収入に直結するAIスキル習得から仕事獲得法まで学べる!
- 今すぐ申し込めば、超有料級の12大特典も無料でもらえる!
\ 累計受講者10万人突破 /
無料AIセミナーを見てみるAIグラビアとは?話題になっている理由
最近、SNSやネット広告でやたらと目にする「AIグラビア」。一体何なのか、なぜこんなに話題になっているのか、まずは基本から押さえていきましょう!
AIグラビアの定義と仕組み


AIグラビアとは、画像生成AIを使って作られた架空のグラビアアイドルやモデルの画像のことです。Stable DiffusionやMidjourneyといった画像生成AIに、プロンプト(呪文)と呼ばれる指示文を入力することで、実在しない人物のグラビア写真を生成できるんです。
従来のCGとの大きな違いは、誰でも簡単に、短時間で、リアルな画像を作れるという点にあります。専門的な3Dモデリング技術がなくても、適切なプロンプトさえ用意できれば、本物と見分けがつかないほどのクオリティの画像が数分で完成してしまうんですね。
なぜ今、AIグラビアが注目されているのか
AIグラビアが急速に広まった背景には、いくつかの理由があります。
まず、技術の急速な進化が挙げられます。2022年頃から画像生成AIの性能が飛躍的に向上し、以前は明らかに「CG」とわかっていた画像が、今では「本物かAIか」を見分けるのが難しいレベルになってきました。肌の質感や髪の毛の流れ、光の当たり方まで、驚くほどリアルに再現できるようになったんです。
次に、制作コストの圧倒的な安さも大きな要因です。通常のグラビア撮影では、モデルのギャラ、カメラマンの費用、スタジオ代、衣装代など、様々なコストがかかります。しかしAIグラビアなら、PCと画像生成ツールさえあれば、ほぼ無料で大量の画像を生成できてしまうんですね。
そして、2023年6月には週刊プレイボーイが「AIグラビアアイドル・さつきあい」のデジタル写真集を発売するという出来事がありました。大手出版社が商業的にAIグラビアに踏み込んだことで、一気に話題となったんです。ただし、この写真集は様々な批判を受けて、わずか数日で販売終了となってしまいました…。
賛否両論が渦巻くAIグラビアの現状
現在、AIグラビアをめぐっては賛否両論が激しく対立しています。
肯定派の意見としては、「技術の進歩がすごい!」「創作の自由が広がった」「誰でもクリエイターになれる」といった声があります。特にデジタルネイティブ世代の若者には、AIグラビアを普通に受け入れている人も多いんですよね。InstagramやTikTokで日常的に写真を加工している世代にとって、AI生成画像も「加工の延長」として違和感が少ないようです。
一方で、否定派からは強い批判も上がっています。「気持ち悪い」「不自然で違和感がある」といった感覚的な拒否反応から、「実在するモデルの仕事を奪う」「学習データの著作権が不透明」「肖像権侵害の可能性」といった倫理的・法的な懸念まで、様々な問題点が指摘されているんです。
この賛否両論の背景には、単なる好みの問題だけでなく、技術の進化スピードに法整備や社会の価値観が追いついていないという現実があります。AIグラビアが「気持ち悪い」と感じられる理由も、実はこうした複雑な背景と深く関わっているんですね。
AIグラビアが「気持ち悪い」と言われる7つの理由
それでは、AIグラビアに対して多くの人が「気持ち悪い」と感じてしまう理由を、7つに分けて詳しく解説していきます!
理由①:不自然な完璧さ
AIグラビアを見たとき、最初に感じる違和感の正体は「完璧すぎる美しさ」にあります。


AIが生成する画像は、シミ、シワ、毛穴、ニキビ跡といった人間なら誰もが持っている肌の特徴が一切ありません。まるで陶器のように均一で滑らかな肌、寸分の狂いもない左右対称の顔、現実の人体構造では実現不可能なプロポーション…。こうした「完璧すぎる要素」が、逆に私たちに不自然さを感じさせてしまうんです。
実は人間って、完璧な美しさよりも「ちょっとした欠点」や「個性的な特徴」に魅力を感じるものなんですよね。例えば、ちょっと歯並びが悪かったり、左右の目の大きさが微妙に違ったり、そういった「人間らしいズレ」があるからこそ、記憶に残る顔になるんです。
AIグラビアの完璧さは、まるで「福笑い」のように理想的なパーツを寄せ集めただけの状態。どれも美しいパーツなのに、組み合わさると「見たことがあるようで、見たことがない」不思議な顔になってしまうんですね。
理由②:「不気味の谷」現象
「不気味の谷」という言葉を聞いたことはありますか?これは日本のロボット工学者・森政弘さんが提唱した理論で、AIグラビアの気持ち悪さを説明する上でとても重要な概念なんです。
簡単に説明すると、ロボットや人工物が人間に似れば似るほど親近感が湧くのですが、ある一定のラインを超えると突然、強烈な不快感や恐怖を感じるようになるという現象のこと。そしてさらに人間に近づくと、再び親近感が回復するというグラフを描きます。
AIグラビアは、まさにこの「谷底」に落ち込んでいる状態なんですね。ほぼ人間に見えるのに、どこか決定的に違う。この「ほとんど人間だけど完全には人間じゃない」という微妙な領域が、私たちの本能的な警戒心を刺激してしまうんです。
これは進化の過程で獲得した防衛本能の一種とも言われています。「何か変だ」と感じた対象に警戒することで、病気や危険を避けてきた名残なのかもしれませんね。
理由③:目に感情が宿っていない
「目は口ほどに物を言う」という言葉がありますよね。実は、AIグラビアの「気持ち悪さ」を語る上で、この「目」の問題はとても大きいんです。
人間の目には、言葉では表現できない複雑な感情や生命力が宿っています。喜び、悲しみ、怒り、不安…そういった感情が、瞳の輝きや視線の動き、まばたきのタイミングなど、無数の要素として表れるんですね。


しかしAIグラビアの目を見ると、表面的には笑っているように見えても、目の奥に何も感じられないんです。虹彩の描写が不自然に均一だったり、光の反射具合がリアルじゃなかったり、「目が笑っていない」状態になってしまうことが多いんですよね。
私たちの脳は、他者の目から膨大な情報を読み取るよう進化してきました。だからこそ、AIグラビアの「魂のない目」に対して、本能的に「これは人間じゃない」と気づいてしまうんです。この感覚が、強い違和感や不快感につながっているんですね。
理由④:個性の欠如
AIグラビアの画像を何枚か見ていると、ある共通点に気づきませんか?そう、どの画像も似たような顔立ちになってしまうんです。


これは、AIが「多くの人が美しいと評価する特徴の平均値」を学習しているから。大きな瞳、小さな顔、高い鼻、ぷっくりとした唇…といった、いわゆる「理想的な美の要素」を組み合わせているため、結果的にステレオタイプな美しさになってしまうんですね。
でも人間の魅力って、そういった「平均的な美しさ」だけじゃないですよね。ちょっと変わった笑い方、独特の雰囲気、その人の経験や人生が滲み出る表情…そういった「その人らしさ」があるからこそ、魅力的に感じるものなんです。
AIグラビアには、そうした「背景」や「物語」を感じさせる要素が欠けています。どれだけ美しくても、心に響かない、記憶に残らない。「美しいけど、何か足りない」という感覚が、結果的に「気持ち悪い」という印象につながってしまうんですね。
理由⑤:肌の質感が不自然


実は、AIグラビアの「気持ち悪さ」を決定づける大きな要因が、この肌の質感なんです。
人間の肌は、角質細胞がレンガのように積み重なってできています。だから、どんなに肌が綺麗な人でも、拡大して見れば必ず微細な凹凸があるんですね。この凹凸が光を複雑に反射することで、私たちは「自然な肌の質感」を認識しているんです。
ところがAIグラビアの肌は、まるでプラスチックやシリコンのように、異様にツルツルとした質感になってしまうことが多いんです。光の反射が不自然に強かったり、逆に全く反射しなかったり。この「のっぺり感」が、人間の肌とは決定的に違うと脳が判断してしまうんですね。
現時点のAI技術では、目・鼻・口といった顔のパーツの生成には力を入れているものの、肌の質感までは十分に考慮されていないようです。この技術的な限界が、「リアルなようでリアルじゃない」という気持ち悪さを生み出しているんです。
理由⑥:倫理的な問題
ここまでは主に「見た目」の問題を扱ってきましたが、AIグラビアへの不快感は、こうした倫理的な懸念からも生まれています。
AIグラビアを生成するには、大量の画像データを学習させる必要があります。でも、その学習データって、どこから来ているんでしょうか?インターネット上にある無数の写真やグラビア画像を、無断で使っている可能性が高いんです。
つまり、実在するモデルやグラビアアイドルの画像が、本人の許可なく勝手に学習データとして使われているかもしれない。さらに言えば、あなた自身がSNSに投稿した写真が、知らないうちにAIの学習に使われている可能性だってあるんです。
「自分の顔や体型が、知らないうちにAIグラビアに使われているかも…」と考えると、ゾッとしますよね。こうした肖像権やプライバシーの問題、データの出処の不透明さが、AIグラビアに対する不信感や嫌悪感を生み出しているんです。
理由⑦:現実との乖離
最後に挙げる理由は、AIグラビアが提示する非現実的な美の基準です。


AIが生成する体型は、しばしば人間の骨格構造を無視した極端なプロポーションになっています。ウエストが細すぎたり、胸が大きすぎたり、足が長すぎたり…。物理的にありえない体型なのに、一見リアルに見えてしまうから余計に厄介なんです。
この「現実離れした美の基準」が広まることで、特に若い世代への悪影響が懸念されています。「こんな体型にならなきゃ」「こんな顔じゃないとダメなんだ」と、不健康な美意識を植え付けてしまう危険性もあるんですね。
実際に、美容整形外科医の中には「AIグラビアの画像を見せて『こういう顔になりたい』と言ってくる患者さんが増えた」と報告している人もいるそうです。
ここまで、AIグラビアが「気持ち悪い」と言われる7つの理由を見てきました。技術的な限界から、心理学的な要因、倫理的な問題まで、様々な角度からその「気持ち悪さ」の正体が見えてきましたね!
世代間で異なる?AIグラビアへの感じ方
実は、AIグラビアへの感じ方って、年齢や育った環境によってかなり違うんです。ここでは、世代によって異なる反応について見ていきましょう!
デジタルネイティブ世代は違和感を感じにくい
興味深いことに、若い世代、特にZ世代やα世代と呼ばれるデジタルネイティブ世代は、AIグラビアに対してそこまで強い違和感を感じていないんです。
その理由は、彼らの日常的な視覚体験にあります。InstagramやTikTok、Snapchatといったアプリでは、フィルターやエフェクトを使って写真を加工するのが当たり前ですよね。肌を滑らかにしたり、目を大きくしたり、顔の輪郭を細くしたり…こうした加工は、もはや「特別なこと」ではなく、自己表現の一部として受け入れられているんです。
つまり、デジタルネイティブ世代にとって、「加工された美しさ」が既にスタンダードなんですね。だからAIグラビアを見ても、「加工の延長線上にあるもの」として自然に受け入れられるわけです。
写真加工文化とAI画像の親和性
もっと面白いのが、若者たちが自分で投稿する写真が、どんどん「AI的な美しさ」に近づいているという事実なんです。


SNSにアップされる写真を見てみると、肌の質感を均一化し、目を大きく見せ、顔の輪郭を整え、体型を理想化するなど、まるでAIが生成したような見た目に加工されていることが多いんですよね。つまり、人間がAIに歩み寄っている状態なんです!
この現象を見ると、AIグラビアの「不自然な美しさ」が不自然に感じられないのも納得できます。彼らにとっては、日々見慣れた視覚言語の一つに過ぎないんですね。
一方で、こうした加工文化に慣れていない世代にとっては、AIグラビアの加工された美しさが極端に感じられ、違和感や嫌悪感につながってしまうんです。
「老害化」しないための意識のアップデート
ここで大事なのは、AIグラビアに違和感を覚えることが「悪い」わけではないということ。ただし、新しい価値観を頭ごなしに否定してしまうのは避けたいところです。
実は、「AIグラビアが気持ち悪い」と強く拒否反応を示すこと自体が、変化する社会や文化についていけなくなっている兆候かもしれません。いわゆる「老害化」ですね。
だからといって、無理に受け入れる必要はありません。大切なのは、なぜ若い世代が受け入れているのか、その背景を理解しようとする姿勢を持つことなんです。
ちなみに、若者たちも決してAIと現実の区別がついていないわけではありません。むしろ彼らは、現実と仮想の境界を流動的なものとして捉え、両者を自在に行き来できる柔軟性を持っているんですね。
AIグラビアへの感じ方の違いは、単なる世代間ギャップではなく、視覚文化そのものが変化している証なのかもしれません。
AIグラビアの技術的な課題と今後の展望
ここまでAIグラビアの問題点を見てきましたが、技術は日々進化しています。現在の課題と、これからどう発展していくのか見ていきましょう!
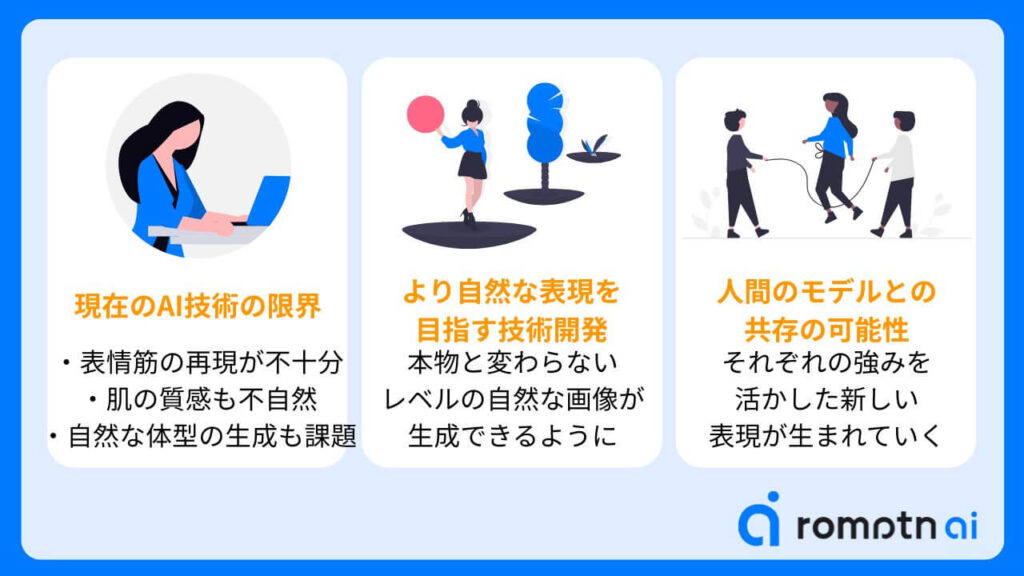
現在のAI技術の限界
AIグラビアが抱える「気持ち悪さ」の多くは、実は技術的な限界に起因しています。
まず、表情筋の再現が不十分なんです。人間の顔には約30種類の表情筋があり、これらが複雑に動くことで微妙な感情表現が生まれます。しかし現在のAI技術では、こうした繊細な筋肉の動きまでは完全に再現できていないんですね。だから「笑っているのに目が笑っていない」といった不自然な表情になってしまうんです。
また、肌の質感についても同様です。人間の皮膚は何層にも重なった複雑な構造をしていて、光の当たり方によって様々な表情を見せます。でもAIは、こうした微細な質感の再現が苦手。結果として、のっぺりとした人工的な肌になってしまうんですね。
さらに、物理法則に基づいた自然な体型の生成も課題です。AIは学習データから「美しい」とされる特徴を抽出しますが、人体の骨格構造や筋肉のつき方といった物理的な制約を十分に理解していないため、ありえないプロポーションを生成してしまうことがあるんです。
より自然な表現を目指す技術開発
とはいえ、AI技術の進化スピードは驚異的です。現在、これらの課題を解決するための研究開発が世界中で進められています。
例えば、表情の自然さを向上させるために、実際の人間の表情筋の動きをデータ化して学習させる試みが行われています。また、肌の質感についても、光の反射や散乱を物理的にシミュレーションする技術の導入が進んでいるんですね。
加えて、倫理面でも進展が見られます。学習データの透明性を確保するための仕組みや、生成された画像に「AI生成である」と分かる電子透かしを埋め込む技術なども開発されているんです。
おそらく数年後には、今私たちが感じている「不気味の谷」を越えて、本物と見分けがつかないレベルの自然な画像が生成できるようになるでしょう。
人間のモデルとの共存の可能性
「AIが進化したら、人間のモデルは必要なくなるの?」という心配の声もよく聞きますが、完全に取って代わる可能性は低いと考えられています。
なぜなら、人間のモデルにはAIには再現できない価値があるからです。その人の個性、表情の豊かさ、撮影現場での偶然生まれる奇跡的な一瞬、カメラマンとのコミュニケーションから生まれる化学反応…こういった要素は、簡単にAIで置き換えられるものではありません。
むしろ今後は、AIと人間のモデルが共存し、それぞれの強みを活かした新しい表現が生まれていくのではないでしょうか。
例えば、人間のモデルをベースにAIで理想的なライティングや背景を生成したり、逆にAIが生成したポーズや構図を参考に実際の撮影を行ったり。AIと人間のコラボレーションによる、これまでにない創作の可能性が広がっているんです。
技術の進化は止まりません。大切なのは、その技術をどう使うか、人間とどう共存させていくか、という私たち自身の選択なんですね!
AIグラビアは産業にどんな影響を与えるのか?
AIグラビアの登場は、グラビア業界だけでなく、クリエイティブ産業全体に大きな波紋を広げています。実際にどんな影響があるのか見ていきましょう!

モデルや写真家の仕事への脅威
まず気になるのが、既存のクリエイターへの影響ですよね。
従来のグラビア撮影では、モデル、カメラマン、ヘアメイク、スタイリスト、レタッチャーなど、多くの専門家が関わってきました。しかしAIグラビアなら、PCひとつで、これらすべての役割を代替できてしまうんです。

実際に、一部の広告やWEBメディアでは、コスト削減のためにAI生成画像を採用する動きが出始めています。「好きなグラビアアイドルの活躍の場が減ってしまうのでは…」「写真家としての技術や感性が軽視されるのでは…」という不安の声は、決して大げさではないんですね。
ただし、完全に仕事が奪われるかというと、そうとも限りません。人間のモデルにしか出せない魅力、プロの写真家だからこそ捉えられる瞬間というのは確実に存在します。むしろ問題なのは、低予算の案件から徐々にAIに置き換わっていくことなんです。
制作コストの大幅削減
AIグラビアの最大の強みは、何といってもコストパフォーマンスの高さです。
通常のグラビア撮影には、モデルのギャラだけでも数万円から数十万円、さらにスタジオ代、カメラマンの費用、衣装代、レタッチ費用など、トータルで数十万円から数百万円かかることも珍しくありません。
それに対してAIグラビアは、画像生成ツールの月額料金(無料〜数千円程度)と、PCの電気代くらい。一度プロンプトを作ってしまえば、何百枚でも量産できてしまうんです。
この圧倒的なコスト差は、特に予算の限られた小規模事業者にとって魅力的ですよね。ただし、安易にAIに飛びつくことのリスクもあります。先ほど紹介した週刊プレイボーイの事例のように、倫理的な問題や批判によって、結局販売中止に追い込まれるケースもあるんです。
新たな表現方法やビジネスチャンスの創出
一方で、AIグラビアは新しい可能性も開いています。
例えば、これまで予算的に無理だったクリエイターが、AIを使って自分のビジョンを形にできるようになりました。また、AIと人間のモデルを組み合わせた新しい表現方法も生まれつつあります。人間のモデルを撮影した写真をベースに、AIで背景やライティングを理想的に加工したり、逆にAIが生成した構図を参考に実写撮影を行ったり。
さらに、「AIディレクター」「プロンプトエンジニア」「AI画像の品質管理者」といった、新しい職種も登場しています。技術の進化で失われる仕事がある一方で、新しい仕事も確実に生まれているんですね。
重要なのは、変化に適応していく柔軟性です。「AIに仕事を奪われる」と悲観的に考えるのではなく、「AIを使いこなすスキルを身につける」という前向きな姿勢が、これからのクリエイターには求められているのかもしれません。
業界全体としては、過渡期の混乱を経て、やがてAIと人間が共存する新しい形に落ち着いていくでしょう。その過程で、私たちがどんな選択をしていくかが問われているんです!
※「プロンプトエンジニア」については、下記記事で詳しく解説しています。
AIグラビアで収益化は可能?気をつけるべきポイント
ここまでAIグラビアの問題点を見てきましたが、「実際に稼げるの?」という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。収益化の現状と注意点を見ていきましょう!
AIグラビアの収益化の現状
結論から言うと、AIグラビアで収益化すること自体は可能です。実際に、写真販売サイトやファンティア、FantiaなどのプラットフォームでAIグラビア写真集を販売して収益を得ている人も存在します。
ただし、週刊プレイボーイの事例が示すように、商業化にはまだまだハードルが高いのが現状です。大手が参入しても批判を受けて撤退するくらいですから、個人で取り組む場合はさらに慎重になる必要があるんですね。
また、AIグラビアは供給量が爆発的に増えているため、競争も激しくなっています。「誰でも簡単に作れる」ということは、裏を返せば「差別化が難しい」ということでもあるんです。
※詳しくは、下記記事で解説しています。
著作権や肖像権の注意点
AIグラビアで収益化を目指す上で、絶対に押さえておくべき法的リスクがあります。
まず、学習データの問題です。画像生成AIは、インターネット上の大量の画像を学習していますが、その中には著作権で保護されたグラビア写真も含まれている可能性が高いんです。「AIが生成したから著作権フリー」というわけではなく、学習元のデータに問題があれば、法的トラブルに巻き込まれるリスクがあります。
次に、肖像権の問題。実在する芸能人やモデルに似た画像を生成して販売すると、肖像権侵害で訴えられる可能性があります。「たまたま似ているだけ」という言い訳は通用しないケースもあるので要注意です。
さらに、各プラットフォームの規約も頻繁に変更されています。現時点では販売可能でも、突然規約が変わって販売停止になる可能性もあるんですね。
倫理的に配慮した制作方法
法的なリスクだけでなく、倫理的な配慮も欠かせません。
まず、生成した画像が「AI生成である」ことを明記することが重要です。実写と偽って販売すると、詐欺だと見なされる可能性もあります。透明性を保つことは、信頼構築にもつながるんですね。
また、過度に性的な表現や、未成年に見える画像の生成は絶対に避けましょう。法的にグレーゾーンだとしても、モラルとして許されない領域があることを認識する必要があります。
加えて、実在するグラビアアイドルやモデルの仕事を奪うような形での商業利用は、業界全体への配慮として控えるべきかもしれません。
もしAIグラビアで収益化をしたくても、これらのを独学で学ぶのは大変ですよね。実は、AI画像生成の技術を体系的に学べるセミナーなども開催されているんです!
累計受講者10万人突破/
AIグラビアの収益化は、可能性もあればリスクもあります。軽い気持ちで始めると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、しっかりと知識を身につけてから取り組むことをおすすめします!
※ぜひ、こちらの記事とセミナーをチェックしてみてください。
【FAQ】AIグラビアに関するよくある質問
最後に、AIグラビアについてよく寄せられる質問にお答えしていきます!
- QAIグラビアは完全に人間のモデルに取って代わりますか?
- A
完全に置き換わる可能性は低いです。人間のモデルが持つ個性や表情の豊かさ、その人自身のストーリー性は、AIには簡単に再現できません。むしろ今後は、AIと人間が共存し、それぞれの強みを活かした新しい表現が生まれていくでしょう。
- QAIグラビアを本物と見分ける方法はありますか?
- A
いくつかチェックポイントがあります。目の虹彩の不自然さ、肌の質感ののっぺり感、髪の毛の流れの違和感、背景との境界の不自然さなどを見ると見分けやすいです。ただし技術の進化により、見分けはどんどん難しくなっています。
- QAIグラビアの技術は今後どのように発展しますか?
- A
より自然な表情や肌の質感の再現、物理的に正しい体型の生成など、人間らしさを追求する方向に進化していくと予想されます。同時に、倫理的な配慮や透明性を確保するための技術開発も進められるでしょう。
- QAIグラビアの制作に法的な問題はありませんか?
- A
現状では法整備が追いついていないグレーゾーンが多いです。学習データの著作権問題、実在する人物に似せた場合の肖像権侵害のリスクなどがあります。商業利用する場合は特に慎重な判断が必要です。
- QAIグラビアで本当に稼ぐことは可能ですか?
- A
可能ですが、ハードルは高いです。法的リスクの管理、倫理的な配慮、プラットフォームの規約順守など、クリアすべき課題が多くあります。また競争も激しいため、単に美人画像を作るだけでは差別化が難しいのが現状です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
AIグラビアが「気持ち悪い」と言われる理由から、技術的な課題、産業への影響、そして収益化の可能性まで詳しくご紹介しました!
この記事で紹介したことをまとめると次のようになります。
- AIグラビアの「気持ち悪さ」は、不自然な完璧さや「不気味の谷」現象、個性の欠如など複数の要因から生まれている
- 世代によってAIグラビアへの感じ方は大きく異なり、デジタルネイティブ世代は比較的受け入れやすい
- AI技術は急速に進化しているが、表情や肌の質感など、まだ人間らしさの再現には課題が残っている
- AIグラビアは既存のクリエイターの仕事に影響を与える一方で、新しいビジネスチャンスも生み出している
- 収益化は可能だが、著作権や肖像権などの法的リスク、倫理的な配慮が必要
AIグラビアに違和感を覚える方も、技術の可能性に興味がある方も、この記事が理解を深めるきっかけになったのではないでしょうか?
もし「AIグラビアの作り方を本格的に学んでみたい!」「AI技術を使った副業に挑戦してみたい!」という方は、体系的に学べるセミナーで基礎から学んでみるのもおすすめです。技術は日々進化していますので、正しい知識を身につけて、新しい可能性にチャレンジしてみてくださいね!
累計受講者10万人突破/
※AIグラビアの作り方は、下記記事で詳しく解説しています。
romptn aiが提携する「SHIFT AI」では、AIの勉強法に不安を感じている方に向けて無料オンラインセミナーを開催しています。
AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。
AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。
\累計受講者10万人突破/