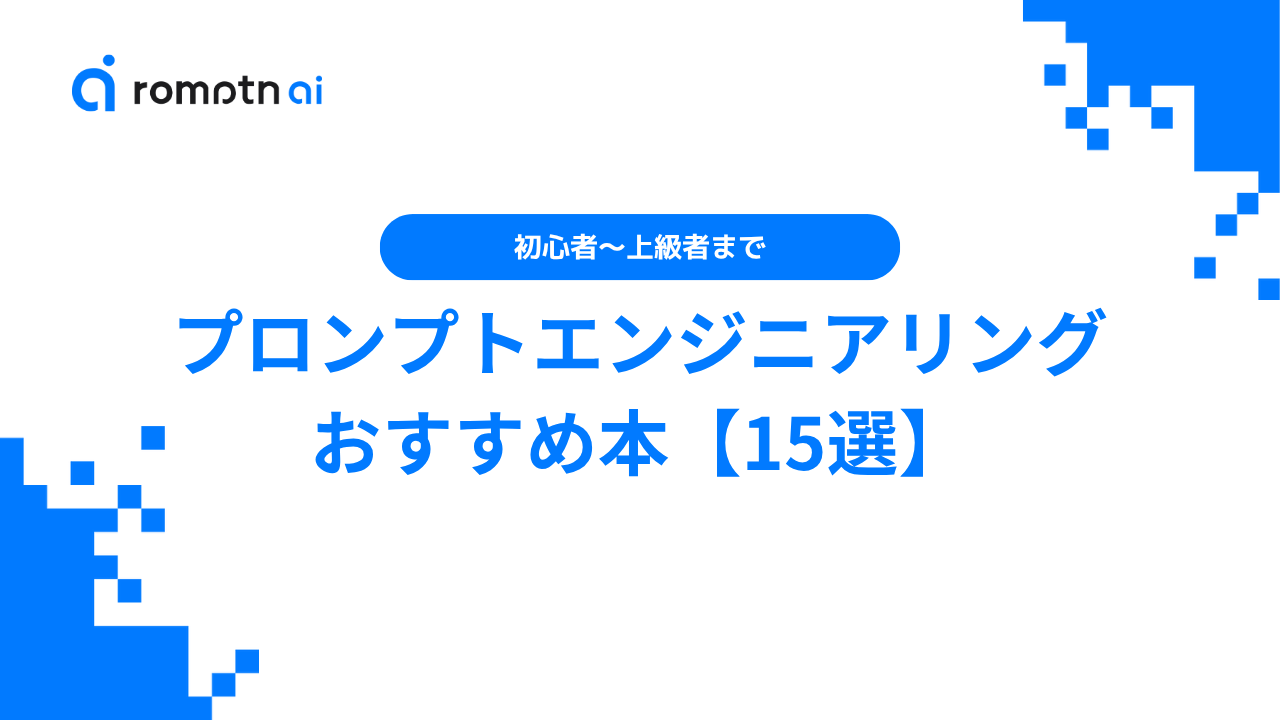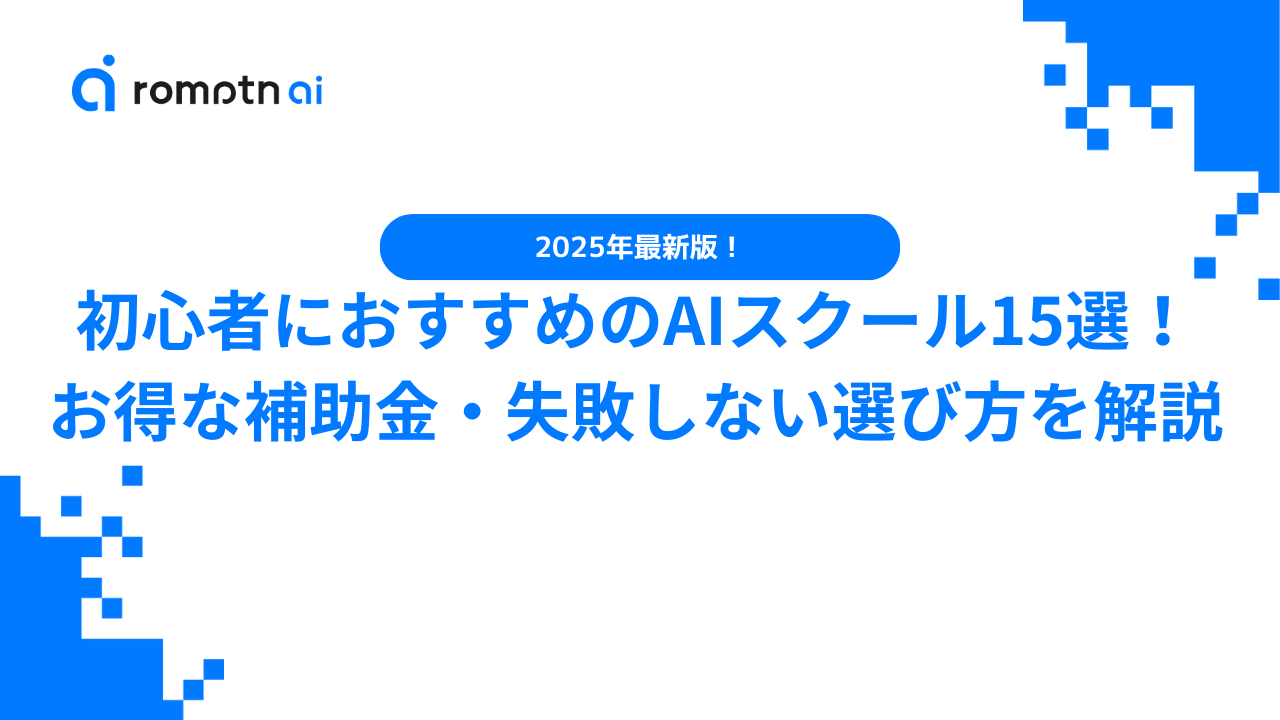生成AIを最大限に活用するために欠かせない「プロンプトエンジニアリング」。ChatGPTやClaude、Geminiなどの生成AIから質の高い回答を引き出すには、適切なプロンプト(指示文)を設計するスキルが重要です。
プロンプトエンジニアリングの需要が高まる中、初心者向けの入門書から実務で使える実践的な専門書まで、数多くの本が出版されています。しかし、「どの本を選べばいいのか分からない」「自分のレベルに合った本はどれ?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、プロンプトエンジニアリングを学べるおすすめの本を、初心者・中級者・上級者のレベル別に15冊厳選して紹介します。さらに、本を選ぶ際の重要なポイントや、本以外の効果的な学習方法についても解説しているので、これから学習を始める方もスキルアップを目指す方も、ぜひ参考にしてください。
📖この記事のポイント
- プロンプトエンジニアリングの本を選ぶ際は、自分のレベルに合ったものを選ぶことが重要
- プロンプトエンジニアリングを学べる本は、実践的なプロンプト集から理論的な解説書まで幅広く出版されている
- 本での学習と並行して、実際に生成AIを使ってプロンプトを試したり、Prompt Engineering Guideなどの学習サイトを活用したりすることで、より実践的なスキルが身につく
- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!
- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!
\ 累計受講者10万人突破 /
無料特典を今すぐ受け取るプロンプトエンジニアリングとは?【基礎知識】

プロンプトエンジニアリングとは、AIから求めているアウトプットを得るためにA Iに出す指示や命令を設計し最適化するスキルのことです。
プロンプトの内容によってAIによる出力結果は大きく異なるため、プロンプトエンジニアリングを理解しておくことはAIの利用に大きく影響するものといえます。
高品質なアウトプット、ビジネスレベルでの使用などを求めるのであれば、適切に設計されたプロンプトが必要不可欠です。
例えば、AIを使って画像を生成したい場合「格好いい画像を作って」というだけでは自身がイメージるす画像をアウトプットしてもらえない可能性が高いです。
ChatGPTをはじめとした生成AIの普及によって、プロンプトエンジニアリングへの注目が集まっています。
プロンプトエンジニアリングについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
また、プロンプトエンジニアになるための方法については以下の記事で詳しく解説しています。
たった2時間の無料セミナーで
会社に依存しない働き方&AIスキル
を身につけられる!
今すぐ申し込めば、すぐに
月収10万円UPを目指すための
超有料級の12大特典も無料!
プロンプトエンジニアリング初心者におすすめの本8選
ここではプロンプトエンジニアリングに初心者が、プロンプトエンジニアリングの基本や概要を理解する際におすすめの本を紹介します。何から勉強すればいいのかわからないといった人は、ぜひ参考にしてください。
1.プロンプトエンジニア1年目が学ぶこと
こちらの本は、プロンプトエンジニアリングの基礎から応用までを学べる入門書という位置付けの一冊です。生成AIの活用方法を詳しく解説し、どうすればAIのアウトプットの質を高められるのかヒントを提供してくれます。
プロンプトエンジニアリングと聞くと難しそうなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、この本では難しい概念はできるだけ取り除いたうえで初心者でも理解できるような内容となっています。
例えば、プロンプト設計における基本ポイントや、大規模言語モデル(LLM)がどのようにプロンプトを理解し、回答を生成するのかといった仕組みなどについても解説されています。
本のタイトルにもなっているように、プロンプトエンジニアリング1年目の人に必要なスキルや知識をテーマとしているため、初心者の方はぜひチェックしてみてください。
| 著者 | ChatGPTプロンプトエンジニアナツキ 清水昴 |
| 価格 | 99円 |
| 出版年 | 2023年9月 |
2.図解 すぐに使えるChatGPTプロンプト集
この本は、ChatGPTで使用できる便利なプロンプトを数多く取り上げている実用的な一冊です。ビジネスシーンや日常生活において、効率的にChatGPTを使いたい人向けに、図解を用いながらプロンプトの活用方法を解説しています。
ChatGPTの基本的な機能や操作方法といった基礎を踏まえたうえでプロントをどのように使えばいいのかを学べる仕組みとなっているため、初心者の方でも読み進めやすいでしょう。
メールを自動作成する、レポートを作成する、データ分析を行うなど、具体的なシーンを想定したプロンプト例も多数紹介されており、コピペしてすぐに実践することも可能です。
| 著者 | ChatGPTサポーターもぐ Kawaii出版 |
| 価格 | 990円 |
| 出版年 | 2023年8月 |
3.プログラミング知識ゼロでもわかる プロンプトエンジニアリング入門
プロンプトエンジニアリングの基本から実践的なテクニックまで取り上げている入門書的な位置付けの一冊です。
本のタイトルにもあるように、プログラミングの知識がない人でも理解できるような内容となっているため、AIに興味があるものの技術的なバックグラウンドがなくて不安に感じている人にもおすすめです。
本では、そもそもプロンプトとはなんなのか、LLMがどのようにしてアウトプットを生成するのか、プロンプトがAIのアウトプットにどのように影響するのかといった基本的な内容をしっかりと解説してくれています。
また、具体的なプロンプトの設計方法やさまざまなシナリオを想定したプロンプトなど実践的な内容も幅広く取り扱っている点が特徴です。
中でも、文章の生成やアイデア発想などを行う際に役立つプロンプトが豊富であるため、そういった目的でAIを使用する方はぜひチェックしてみてください。
| 著者 | 掌田 津耶乃 |
| 価格 | 2,750円 |
| 出版年 | 2023年11月 |
4.エンジニアのためのChatGPT活用入門 AIで作業負担を減らすためのアイデア集
こちらは、エンジニアがChatGPTを使用して作業負担を軽減し、業務効率化を実現するための具体的なアイデアを取り上げている実用的なアイデア集です。
自動ドキュメント生成やリサーチ、分析など、エンジニアが日々の業務の中で取り組むタスクを簡単に解決できる方法が示されており、エンジニアの作業効率を高める方法を学べる一冊となっています。
また、システムやアプリの開発にあたってどのようなプロンプトを作成すればChatGPTから適切なアウトプットを引き出せるのか、実際にWebアプリを作りながら、プロンプトの実例を紹介しているため、実践を想定しながら読み進めることができます。
開発業務にChatGPTを使用したい方が最初に読むべき一冊だといえるでしょう。
| 著者 | 大澤 文孝 |
| 価格 | 2,750円 |
| 出版年 | 2023年12月 |
5.ChatGPT はじめてのプロンプトエンジニアリング
こちらの本は、読者をプロンプトエンジニアリングの世界に導き、AIに慣れ親しんでもらうことを目的とした入門書です。
難しい専門用語は使われておらず、一般的な言葉を使っていかにしてA Iを動かすか、という点を体系的に解説してくれています。
プロンプトを構成要素ごとに分解したうえで、それぞれについてわかりやすく説明し、少しずつ各要素を組み合わせて実践的なスキルを身に付けていく仕組みとなっているためプロンプトを初めて学ぶ人でも理解しやすいでしょう。
仕事や学習、創作などあらゆるシーンを想定した豊富な事例と演習も用意されているため、本で学んだことをそのまま実戦で試すといったことも可能です。プロンプトエンジニアリングの基礎を学び、ChatGPTを自由に使いこなしたい人におすすめの一冊です。
| 著者 | 本郷 喜千 |
| 価格 | 2,200円 |
| 出版年 | 2025年3月 |
6.ChatGPT日本語プロンプトパッケージ150
日本語プロンプトでChatGPTをすぐに活用したい方におすすめの実践的なガイドブックです。
こちらの本では、ライティング、Webマーケティング、ソーシャルメディア、教育・学習、料理など、10以上のカテゴリから厳選された150種類の日本語プロンプトが収録されており、英語が苦手な方でも安心して使えます。さらに、読者限定特典として追加で200種類のプロンプトが用意されており、合計350種類もの日本語プロンプトを活用できます。
何度もテストを繰り返して最適化されたプロンプトは、今すぐコピー&ペーストで使えるため、初心者でも迷わず実践できます。すべてのプロンプトの実例をGPT-4モデルで生成しているため、有料版ChatGPTの契約を検討している方にとっても、GPT-4の回答品質を確認できる判断材料となります。
アメリカで働くエンジニアである著者が、実務経験をもとに厳選したプロンプトが詰まった一冊です。プロンプトの基礎から実践的な活用まで、すぐに役立つ内容が満載で、ChatGPT初心者がプロンプトエンジニアリングのスキルを身につけるための最適な入門書といえます。
| 著者 | Mamoru 著 |
| 価格 | 250円 |
| 出版年 | 2023年03月 |
7.ChatGPTで始めるAI執筆の旅:プロンプトエンジニアリング入門書
ChatGPTを活用してAI執筆の実践的なスキルを身につけたい方におすすめの入門書です。
こちらの本では、約29,000文字のプロンプト例と、約4万8000文字にも及ぶAIとの実際の対話を収録しており、プロンプトエンジニアリングの実践的な流れを体験しながら学べます。難易度の低い順にプロンプト例を紹介しているため、初心者でも無理なく段階的にスキルアップできる構成となっています。
内容は、AIへの基本的な指示の出し方から、仕事や創作への活用、AIとの効果的な共同執筆、プロンプト設計の技術、さらにはAIを使ったプログラミングやゲーム開発まで、幅広いトピックを網羅しています。また、ChatGPTのプラグインや他のAIサービス(BardやBingAI)の活用方法も紹介されており、実用的な知識が満載です。
著者は旅本作家として活動しながらゲーム制作やDTM作曲など多彩な創作活動を行っており、その実践経験に基づいた具体的なノウハウが詰まった一冊です。ChatGPTを使った執筆や創作活動に興味がある方、AIを活用して作業効率を高めたい方に最適な実践ガイドといえます。
| 著者 | kuro 著 |
| 価格 | Kindle版(価格は要確認) |
| 出版年 | 2023年04月 |
8.AI時代の質問力 プロンプトリテラシー
AIとのコミュニケーション能力を高めたい方におすすめの、プロンプトリテラシーに特化した一冊です。
こちらの本では、大規模言語モデルの仕組みとプロンプトエンジニアリングの基本を理解するところから始まり、AIに適切な質問をし、AIとより効果的な対話をするためのプロンプトパターンやトリガープロンプトなど、実践的なテクニックを体系的に学べます。さらに、発展的な技術や最先端のAIエージェントまで、AIとのやりとりを最適化するための知識とノウハウが網羅されています。
具体的な例を挙げながらわかりやすく解説しているため、学生から一般のビジネスパーソンまで幅広く読むことができます。著者は筑波大学と会津大学の准教授として人工生命やウェブサイエンス、計算社会科学を専門とする研究者であり、学術的な裏付けのある確かな内容となっています。
本書を読むことで、AIと効果的に対話するためのスキルや知識が身につき、すぐに日常生活や業務に活かすことができます。ChatGPTなどの生成AIを使いこなし、その可能性を最大限に引き出したい方に最適な実践ガイドといえます。
| 著者 | 岡 瑞起、橋本 康弘 著 |
| 価格 | 1,870円 |
| 出版年 | 2024年07月 |
たった2時間のChatGPT完全入門無料セミナーで ChatGPTをフル活用するためのAIスキルを身につけられる!
今すぐ申し込めば、すぐに
ChatGPTをマスターするための
超有料級の12大特典も無料!
プロンプトエンジニアリング中・上級者におすすめの本7選
続いてはプロンプトエンジニアリングについての基本は理解しており、さらに詳しく勉強したいといった中・上級者におすすめの本を紹介します。
1.ChatGPTを使い尽くす! 深津式プロンプト読本
こちらの本は、ChatGPTを最大限に使いこなすためのプロンプト設計方法を体系的に解説している点が特徴です。
著者は、生成AI活用の第一人者である深津貴之氏考案の「深津式プロンプト」をベースに、ビジネスシナリオを交えながらわかりやすくプロンプトの設計方法を説明しています。
カスタマーサポート、コンテンツ生成、リサーチなど、各種ビジネスシーンで役立つプロンプト例が豊富に紹介されているほか、ChatGPTを活用した作業の自動化やなども取り上げています。
普段の業務でChatGPTをもっと効果的に活用したい方、プロンプトエンジニアリングに興味を持つエンジニアなどにおすすめの一冊です。
| 著者 | 深津 貴之 岩元 直久 |
| 価格 | 2,640円 |
| 出版年 | 2024年8月 |
2.大規模言語モデルを使いこなすためのプロンプトエンジニアリングの教科書
こちらは、ChatGPTをはじめとしたLLMにおけるプロンプトエンジニアリングを網羅的にまとめた一冊です。
LLMにおける応答能力の改善方法や向上テクニックなどは、すでに研究よって明らかにされていますが、この本ではそういった方法やテクニックを詳しく解説しています。
また、プロンプトの構造や言語モデルがどのように動くのかといった動作原理、プロンプト設計における基礎理論といった基本的な部分も取り上げているため、基礎を振り返りつつ、応用を学んでいきたい人にぴったりです。
一般的な業務でAIを使用する方はもちろん、アプリ開発などで使用するエンジニアの方にも役立つ内容となっています。
| 著者 | クジラ飛行机 |
| 価格 | 3,828円 |
| 出版年 | 2024年3月 |
3.思考で差をつけるプロンプトエンジニアリング
こちらの本では、プロンプトエンジニアリングの基本から応用まで詳しく解説しており、ビジネスシーンや日常生活でAIをどのように役立たせるかを具体的に紹介しています。
「思考で差をつける」というように、ただ単にプロンプトを設計するのではなく、効果的な結果を導くためにどのように施行する必要があるのか、プロンプトを工夫する必要があるのか、どういった論理的アプローチが効果的なのかといった点が解説されています。
思考法や論理的アプローチを理解することで、通常のプロンプトでは出せないような、質の高いアウトプットを得ることもできるでしょう。
より高いレベルでAIを活用したい人や、ビジネスシーンでの応用を目指している方におすすめの一冊です。
| 著者 | 新銅将拡 |
| 価格 | 498円 |
| 出版年 | 2024年9月 |
4.生成AIのプロンプトエンジニアリング
生成AIから信頼できる出力を引き出したい方におすすめの包括的な一冊です。
こちらの本では、GPT-3以降の知見をもとに、LLMや画像生成モデルに共通する原則と実践手法を体系化しています。プロンプトの基本原則から、ハルシネーション対策、出力の安定化、評価手法まで、実務で役立つ実践的な内容を幅広くカバーしています。
Jupyter NotebookやGoogle Colabでサンプルコードを実際に動かしながら学べる構成となっており、理論と実践を並行して習得できます。最終章では、それまで学んだ知識を活用して、実際に生成AIアプリケーションを構築する流れまで解説されています。
モデルが進化しても通用する普遍的アプローチが身につく設計となっており、長期的に活用できる知識を得られる点も魅力です。プロンプトエンジニアリングの全体像を体系的に理解したい初心者から、より高度な活用を目指す中級者まで幅広くおすすめできる一冊です。
| 著者 | James Phoenix、Mike Taylor 著 田村 広平、大野 真一朗 監訳 砂長谷 健、土井 健、大貫 峻平、石山 将成 訳 |
| 価格 | 4,840円 |
| 出版年 | 2025年07月 |
5.LLMのプロンプトエンジニアリング
LLMを使って期待通りかつ質の高いアウトプットを引き出したい方におすすめの一冊です。
こちらの本では、LLMの特性を理解するところからスタートしており、そのうえでプロンプトにはどういった要素を組み込むべきなのか、どういった構造にするべきなのかといったプロンプトエンジニアリングのコツを解説しています。
GitHub Copilotの開発者でもあるこちらの本の著者は、開発過程での知見や、評価手法、設計上の判断など、開発の裏側も詳しく解説されており、読み物としても読み応えがあります。
AIアプリの開発の実際を知りたい方や生成AIの可能性・限界を知りたい方に特におすすめです。
| 著者 | John Berryman、Albert Ziegler 著 服部 佑樹、佐藤 直生 訳 |
| 価格 | 4,180円 |
| 出版年 | 2025年05月 |
6.2冊目に学ぶ ChatGPTプロンプト攻略術 実務で使える職種別実践ノウハウ大全
ChatGPTの基礎を理解し、実務での具体的な活用法を知りたい方におすすめの実践的なプロンプト集です。
こちらの本では、ChatGPTを利用した実践的なテクニックを逆引き形式で数多く掲載しており、実務を想定した具体的な事例として紹介しています。職種別に最適化されたプロンプトが収録されているため、自分の業務にすぐに応用できる内容が見つかります。
プロンプトのコツも詳しく解説されており、単なるプロンプト例の羅列ではなく、なぜそのプロンプトが効果的なのかを理解しながら学べる構成となっています。ビジネスシーンでChatGPTをどのように活用できるかのヒントが豊富に含まれており、よく使うプロンプトを型として保存して活用できる実用的なアイデアも満載です。
Amazon限定特典として購入者にはPDFプレゼントもあり、ChatGPTをより使いこなして業務効率化を図りたい方、職種に特化したプロンプト活用法を知りたい方に最適な一冊といえます。
| 著者 | 岡田徹、秋月宏介 著 |
| 価格 | 4,202円(3,820円+税) |
| 出版年 | 2023年12月 |
7.ChatGPT超活用術 仕事で役立つプロンプトの極意 -より深く正しい回答を得る方法-
ChatGPTを業務で最大限に活用したいビジネスパーソンにおすすめの実践的な一冊です。
こちらの本では、対話型生成AIを業務で活用したいが活用方法がわからない方を対象に、会社で実際に使われているリアルな質問事例を目的別に紹介しています。類書でよく見る抽象的な説明ではなく、現実のビジネスシーンで役立つ実践的な情報が満載で、すぐに使える質問事例を豊富に掲載しています。
著者は大手メーカーで製品の研究開発、社内の管理業務、業務効率化に携わり、RPA、Python、生成AIを活用した実務経験を持つ実践家です。その経験に基づいた現場で本当に必要とされるプロンプトのノウハウが詰まっており、読者からは「この本に書いてあることを使って、かなり生産性が向上した」との声も寄せられています。
本書を読めば、生成AIを使いこなすための知識やノウハウが自然と身につき、業務でのAI利用が一段と効率的で効果的になります。ChatGPTをより深く正しく活用して業務効率を大幅に向上させたい方に最適な実践ガイドといえます。
| 著者 | 江坂和明 著 |
| 価格 | 1,980円(1,800円+税) |
| 出版年 | 2024年09月 |
プロンプトエンジニアリングの本を選ぶ際のポイント

ここでは、プロンプトエンジニアリングの本を選ぶ際のポイントを紹介します。プロンプトエンジニアリングをテーマにした本はたくさんあるため、適切な本を選ぶためにもぜひ参考にしてください。
①自分に合ったレベルの本を選ぶ
プロンプトエンジニアリングをテーマにした本を選ぶ場合、自分のレベルを考慮する必要があります。本は初心者向けから上級者向けまであり、本の想定読者はさまざまです。
例えば、初心者であれば、ChatGPTの基本操作やプロンプトの書き方、簡単なテンプレなどを取り扱う入門書が適しているでしょう。プロンプト作成の基礎から学べる本がおすすめです。
また、中級者はそこから少し発展し、プロンプト設計の構造や調整方法、AI活用の実践事例などを取り扱っている本が適していると考えられます。さらに上級者になるとLLM(大規模言語モデル)の仕組みや応用理論などより高度な内容を解説している専門書がおすすめです。
このように、自分のレベルを踏まえたうえで、プロンプトエンジニアリングのスキル習得に適した本を選ぶようにしてください。
②出版年に注意する
プロンプトエンジニアリング本を選ぶ際は、出版年を確認してください。なぜなら、ChatGPTなどの生成AI技術は日々進化しており、1ヶ月前の情報がすでに古い情報となっているケースも珍しくなく、出版年が数年前の書籍だと内容自体も現在のものに合っていない可能性があるためです。
古い情報を扱っている参考書を購入してしまうとプロンプトエンジニアリングの学習にならない可能性があるだけでなく、金銭的にも損をしてしまうため注意してください。最新の生成AIの動向を反映した本を選ぶことが重要です。
③著者の専門分野をチェックする
生成AIやプロンプトエンジニアリングをテーマにした本は多く出版されていますが、著者の専門分野もさまざまであるため、どの分野の人が書いたのかをチェックしてください。
例えば、AIのエンジニアや研究者が著者であれば、技術的・構造的な解説が多くなると考えられます。一方で、マーケターが著者だと、生成AIの実践事例やビジネス応用がメインテーマとなる可能性があります。
著者の専門分野によって取り上げるテーマにも違いが現れると考えられるため、自分がプロンプトエンジニアリングの本で何を知りたいのかを明確にしておくことが大切です。
本以外のリソースでプロンプトエンジニアリングを学ぶ方法

ここまでプロンプトエンジニアリングをテーマにした本を紹介してきましたが、本以外のリソースでも学ぶことは可能です。具体的にどういった方法があるのか解説します。
①実際に生成AIを使う
最も手っ取り早いのは、実際に生成AIを使ってみることです。どういったプロンプトを入力すると自分が求めるアウトプットが出力されるのか、うまく出力されなかったのは何が原因なのかといった点は、自分が経験することでより深く理解できます。
知識をしっかりと学んでから実践しようとする人もいるかもしれません。もちろんそのやり方も間違いではありませんが、実際に自分で手を動かしながら直感的にプロンプトを作成することでより実用的なスキルを身につけることができます。
本で学習しつつ、時々学んだことを実践で使ってみるなどしてみてください。まずは無料で始められるChatGPTやClaude、Google Geminiなどを活用してみましょう。
②Prompt Engineering Guideをチェックする
好きなタイミングでマイペースに勉強を進めたい人には、学習サイトの活用もおすすめです。Prompt Engineering Guideは、プロンプト設計に関する情報が体系的にまとめられているサイトです。
プロンプト設計の原則や事例が体系的に整理されており、ChatGPTなどのLLMの実践的な内容を学べます。こちらは英語サイトですが、翻訳機能を使えば日本語で読むことも可能です。
初心者〜中級者が体系的にプロンプト設計を学ぶ入門書的ポジションとしておすすめのサイトだといえます。
プロンプトエンジニアリングガイドのサイトはこちらです。
③講座・スクールに参加する
対面やオンラインではAIをテーマにしたさまざまな講座やスクールが開講されているため、それに参加して学ぶのも1つの方法です。
講座やスクールを活用するメリットは、講師によるレッスンを受けられるのはもちろん、不明点を気軽に質問できるなど、さまざまなサポートを受けられる点にあります。
わからなくて挫折するといったリスクを低減できるため、初心者は本での学習に加え、講座やスクールへの参加も検討してみるといいでしょう。
おすすめの生成AIスクールについてはこちらの記事で解説しています。
まとめ
今回は、プロンプトエンジニアリングにおすすめの本を15冊紹介しました。この記事のポイントは以下のとおりです。
- プロンプトエンジニアリングの本を選ぶ際は、自分のレベルに合ったものを選ぶことが重要
- 初心者は基本操作やテンプレートを扱う入門書、中級者はプロンプト設計や活用事例を学べる本、上級者はLLMの仕組みや応用理論を解説した専門書がおすすめ
- プロンプトエンジニアリングを学べる本は、実践的なプロンプト集から理論的な解説書まで幅広く出版されている
- 本での学習と並行して、実際に生成AIを使ってプロンプトを試したり、Prompt Engineering Guideなどの学習サイトを活用したりすることで、より実践的なスキルが身につく
今回の内容を参考に、ぜひプロンプトエンジニアリングについての学びを深めてください。