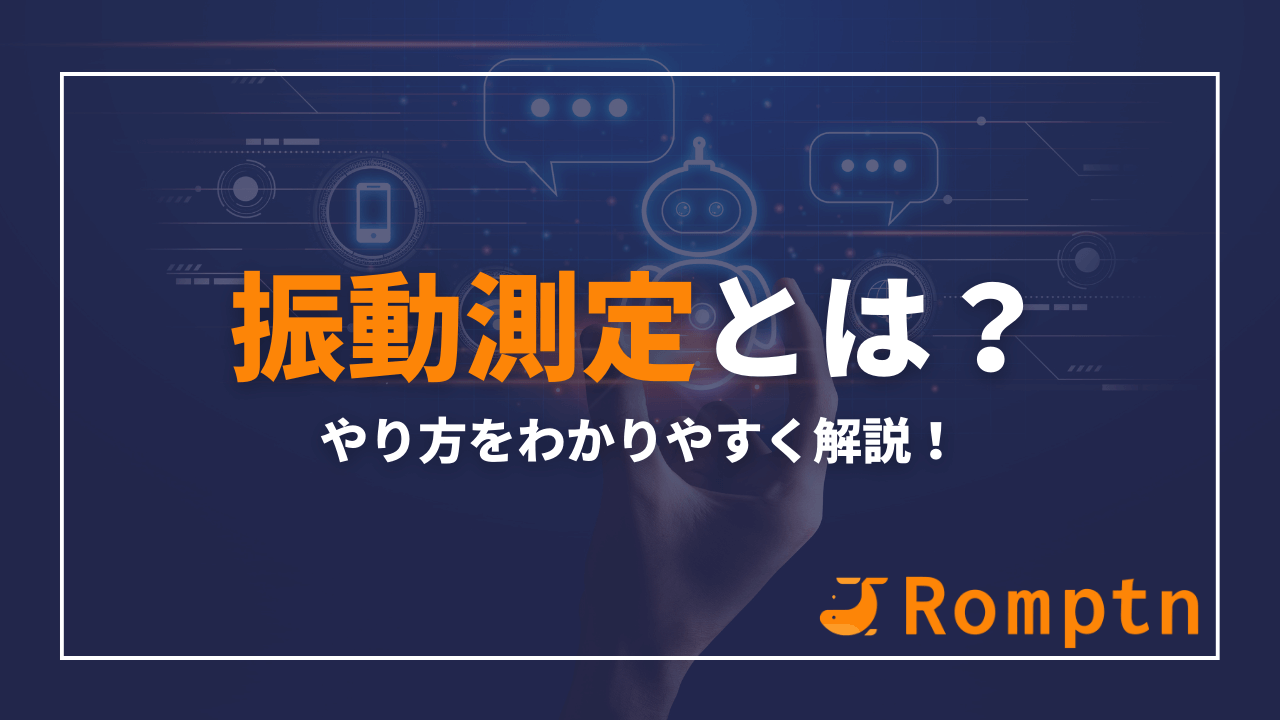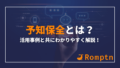設備の故障予兆は、目に見える異常として表れる前に「わずかな振動の変化」として現れます。ポンプやファンの揺れが少しずつ大きくなる、ベアリングが高周波の振動を発し始める──こうした初期症状をつかめるかどうかが、突発停止の回避や品質トラブルの防止に直結します。最近では、振動データをAIで解析して異常を自動検知する取り組みも急速に広がりつつありますが、その効果を最大化するためには“そもそも振動をどう測るか”という本質を理解しておく必要があります。
この記事では、振動測定の基本概念、測定で扱う3つの物理量、測定方法や結果の読み方、そしてAI異常検知へ発展させるためのステップまでを一連の流れで整理します。難しい専門知識がなくても読み進められるように構成しているので、初めて振動測定に触れる方でも「どこから手を付ければよいか」が自然につかめるはずです。
読み終えるころには、振動測定がなぜ予防保全に欠かせないのか、そのデータがAIとどう結びついていくのかが、自分の言葉で説明できる状態になっていることを目指しています。現場の感覚頼りだった点検を“データで理解できるもの”へ変える、その第一歩として役立ててください。
📖この記事のポイント
- 振動測定は設備の初期異常を可視化する基本技術で、予防保全・予兆保全の出発点になる!
- 変位・速度・加速度にはそれぞれ得意分野があり、目的に応じた使い分けが診断精度を左右する!
- 測定点・方向・周波数帯などの測定設計は、データ品質とAI異常検知の精度に直結する重要要素!
- 振動結果は絶対値だけでなくトレンドや周波数スペクトルを見ることで異常の原因を判断しやすくなる!
- AI異常検知は振動データとの相性が良く、巡回測定→常設センサー→AI分析の段階的導入が最も現実的!
- 良質な振動データの蓄積こそがAI活用の成否を決め、予兆保全の高度化につながる!
- たった2時間の無料セミナーで会社に依存しない働き方&AIスキルを身につけられる!
- 今すぐ申し込めば、すぐに月収10万円UPを目指すための超有料級の12大特典も無料でもらえる!
\ 累計受講者10万人突破 /
無料特典を今すぐ受け取る振動測定とは?どんな場面で使われる技術か
振動測定とは、ポンプやモーター、ファンなどの機械設備が発する揺れをセンサーで捉え、数値として評価する技術です。設備の劣化や故障予兆は、温度上昇や異音よりも早い段階で「振動の変化」として現れることが多く、設備管理において最も基本的で効果の高い診断手法のひとつとされています。特に近年では、振動データをAIで解析することで故障予兆をより早く、より高精度に検知する取り組みが広がり、振動測定の重要度が再認識されています。
振動測定の主な目的
振動測定の狙いは、目に見えない初期異常を数値として捉え、突発停止や重大トラブルを未然に防ぐことにあります。経験や勘に頼らずに設備状態を把握できるため、保全業務の標準化にもつながります。
- ベアリング摩耗・アンバランス・ミスアライメントの早期発見
- 据付不良・芯ズレなどの施工品質の確認
- 運転条件(回転数・負荷)の変更による挙動の把握
- 定期点検でのトレンド(経時変化)の管理
どんな設備・現場で活用されているか
振動測定は「回転する設備が多い現場」で特に効果を発揮します。日常的に振動診断が行われる代表的な機器・環境は次のとおりです。
- 製造業:ポンプ、ファン、ブロワ、コンプレッサ、ミキサー
- 生産ライン:モーター、減速機、コンベア駆動部
- プラント設備:冷却塔のファン、攪拌機、回転機群
- ビル設備:空調機、送風機、冷凍機
AI時代に振動測定が注目される理由
AIによる異常検知の精度を高めるには、特徴量として有用な“揺れの変化”を的確に捉えたデータが必要です。振動データはその条件を自然に満たしており、AIとの相性が極めて高い領域と言えます。
- 異常の影響が波形や振幅に表れやすく、数値特徴量として扱いやすい
- 時系列データ・周波数成分など、AI向けの特徴が豊富
- IoTセンサーで常時収集しやすく、データ蓄積が容易
振動測定は、予防保全のための「状態監視の基礎」であると同時に、AIによる自動診断の土台にもなります。正確に測り、意味を理解することが、AI活用の一歩目として極めて重要です。
振動測定で扱う3つの物理量(変位・速度・加速度)
振動を「数値」として扱うときには、主に「変位」「速度」「加速度」という3つの物理量が使われます。同じ振動現象でも、どの物理量で見るかによって見え方や得られる情報が変わります。目的に合った指標を選べるかどうかが、振動測定やAI解析の精度に直結します。
振動変位:低周波・大きな揺れを捉える指標
振動変位は、「ある点がどれだけの距離揺れているか」を表す物理量で、単位は μm(マイクロメートル)や mm が用いられます。回転体のアンバランスや芯ズレなど、ゆっくりとした大きな揺れを評価するのに適しています。
たとえば、据付が緩んで機械全体が揺れているようなケースでは、変位で見ると異常が分かりやすくなります。一方で、高周波の微小な振動は変位では捉えにくいため、他の物理量と組み合わせて使うのが一般的です。
振動速度:設備診断で最も一般的な評価指標
振動速度は、「揺れがどのくらいの速さで動いているか」を表す物理量で、単位には mm/s がよく用いられます。人間が「揺れ」として感じる違和感と相関が高く、ISO規格や各種ガイドラインでも振動速度を基準にした評価方法が多く採用されています。
設備診断の現場では、まず振動速度のrms値(実効値)を見て、「許容範囲内かどうか」「過去と比べてどれくらい変化しているか」を確認します。変位と加速度の中間的な性質を持ち、回転機全般の総合的な振動レベルを評価するのに最もよく使われる指標です。
振動加速度:ベアリング・ギアの初期異常に敏感な指標
振動加速度は、「揺れの速度がどれくらいの勢いで変化しているか」を表す物理量で、単位は m/s² や G(重力加速度)を使います。高周波の細かな振動や衝撃成分に敏感で、ベアリングの転動面の傷、潤滑不良、ギアの欠けなど、初期段階の異常検出に向いています。
AI異常検知の観点でも、加速度データは非常に重要です。高周波側に現れる微妙な変化を特徴量として抽出することで、人の目では気づきにくい初期劣化の兆候を捉えられる可能性が高まります。
| 物理量 | 主な特徴 | 単位の例 | 得意な異常・用途 |
|---|---|---|---|
| 振動変位 | 低周波で大きな揺れを捉えやすい | μm、mm | アンバランス、芯ズレ、据付不良 |
| 振動速度 | 人の感覚に近い振動レベルを評価しやすい | mm/s | 回転機全般の総合的な振動評価 |
| 振動加速度 | 微小・高周波・衝撃的な振動に敏感 | m/s²、G | ベアリング・ギアの初期異常、衝撃診断 |
実務では、どれか1つだけを使うのではなく、「速度で全体レベルを評価し、気になる箇所は加速度で高周波まで確認する」といった形で複数の物理量を組み合わせるケースが一般的です。AIに学習させる際も、変位・速度・加速度のどれを入力とするかによって学習できるパターンが変わるため、目的に応じた選択が重要になります。
振動測定に使う測定器とセンサーの種類
振動測定を行う際には、「何を測るか」と同じくらい「何で測るか」が重要です。測定器やセンサーの種類によって取得できる周波数帯や感度が異なるため、目的に合った機器を選ばないと、本来捉えるべき異常を見逃してしまう可能性があります。ここでは、現場でよく使われる測定器の特徴と、AI活用まで見据えた選び方を整理します。
ポータブル振動計:巡回点検に最適な基本ツール
ポータブル振動計は、設備の近くに行って必要なポイントにセンサーを当て、振動値をその場で測定するタイプの測定器です。多くの現場で「まずはこれから」という位置づけで導入されます。
- メリット:機動性が高く、導入コストも比較的低い。測定の自由度が高く、異常の傾向を手軽につかめる。
- デメリット:データが断片的になりやすく、AI学習用の“連続データ”としては不足しがち。測定者によるばらつきも出る。
週次・月次の巡回点検でトレンドを管理したい場合には非常に便利ですが、AIで高度な異常検知を行うには、より継続的なデータ取得が必要になります。
常設型振動センサー:AI活用の前提になる連続データを取得
常設型振動センサー(加速度ピックアップなど)は、機器に取り付けて連続的に振動データを取得する方式です。IoTゲートウェイやクラウドと接続することで、リアルタイム監視やAI分析が可能になります。
- メリット:連続的なデータが取得でき、異常発生前後の詳細な波形も残せる。トレンド分析や周波数解析に向き、AIの学習データとしても理想的。
- デメリット:取り付け工事、配線、電源確保などが必要。初期費用はポータブルより高め。
重要設備や停止リスクが高い設備では、常設センサーがほぼ必須となりつつあります。「どの周波数帯を捉えられるか」「耐環境性は十分か」など、仕様の確認もポイントです。
三軸加速度センサー:AI解析で特に相性が良い
近年増えているのが「三軸加速度センサー」です。1つのセンサーで水平・垂直・軸方向の3方向の振動を同時に取得できるため、異常の方向性や原因をAIが判断しやすくなります。
- ミスアライメント(軸方向)などの方向性異常の検知がしやすい
- データの一貫性が高く、AIの特徴量として扱いやすい
- IoT用途で小型・低消費電力のものも増えている
センサー選定時に押さえるべきポイント
AIまで見据えた場合、次の性能を重視することで「後から使えないデータになってしまう」リスクを避けられます。
- 周波数帯域:ベアリング診断の場合は数kHz〜数十kHzまで必要
- 感度とノイズ:微小振動を捉えるには感度とノイズフロアの確認が必須
- 取り付け方法:磁石式/ボルト固定/粘着式で精度が変わる
- 耐環境性:水・油・温度の影響を受ける現場ではIP規格の確認が必要
「どのセンサーを選ぶか」は、測定する物理量と同じくらいAI精度に影響します。特に高周波成分を捉えたい場合は、安価なセンサーでは不十分なことも多いため、目的に応じて適切なスペックを選ぶことが重要です。
振動測定のやり方(測定点・方向・周波数帯・手順)
振動測定の精度は、「どこを・どの方向に・どんな条件で測るか」に大きく左右されます。同じ設備でも、測定点や方向を誤るだけで異常の兆候を見逃してしまうことも珍しくありません。ここでは、現場で必ず押さえておきたい基本ポイントと、AIでの解析を前提にした測定設計の考え方を整理します。
測定点:モーター側と負荷側の両方を押さえる
回転機の異常は、発生源の近くで最も顕著に現れます。そのため、測定点は設備の構造に合わせて「どの軸受にどんな負荷がかかるか」を意識して設定する必要があります。
- モーター前後の軸受部:アンバランス・軸曲がり・ミスアライメントの影響が出やすい
- 負荷側(ポンプ・ファン)の軸受部:ポンプ内部の摩耗や羽根車の偏りなどが反映されやすい
- 中間軸・減速機:カップリング不良やギア摩耗の判別に有効
異常の切り分けには「モーター側で強いのか、負荷側で強いのか」という比較が非常に重要です。最低でも両側の軸受で測定するのが基本になります。
測定方向:水平・垂直・軸方向の3方向が理想
振動は方向によって現れ方が異なるため、基本的には次の3方向を測定するのが最も確実です。
- 水平方向:アンバランスの影響が最も出やすい
- 垂直方向:据付剛性や支持条件の影響が出やすい
- 軸方向:ミスアライメントやスラスト荷重に敏感
三軸センサーを使用すれば1台で3方向を同時取得できますが、単軸センサーの場合は測定者の「方向選定のセンス」が精度に大きく影響します。
周波数帯・サンプリング条件:AI精度を左右する重要要素
どれだけ正確に測っても、周波数帯の設定を誤ると異常の特徴を捉えられません。特にベアリングやギアの初期異常は高周波側に現れるため、必要な帯域をカバーできているかは必ず確認すべきポイントです。
- 解析周波数帯:回転数の数倍〜十数倍までが基本。ベアリング診断では5kHz〜30kHz以上が必要なケースも。
- サンプリングレート:ナイキスト周波数(最大周波数の2倍)が十分確保されていることが前提。
- フィルタリング条件:低域ノイズや電気ノイズを除去し、異常に関係する成分をクリアに保つ。
AIで特徴量として扱う場合、高周波の細かなピークやパターンが有効になるため、できるだけ高帯域・高サンプリングで記録できる環境を整えることが推奨されます。
測定手順:現場で迷わないための基本フロー
- 対象設備と目的(予兆検知・据付確認など)を明確にする
- 図面・構造を確認し、測定点と方向を正しく設定する
- センサー取り付け部の清掃・固定を行い、測定条件を統一する
- 運転条件(回転数・負荷)を可能な範囲で一定に揃えて測定する
- 測定値を時系列で記録し、同条件で繰り返し比較する
AI活用を目指す場合でも、この基本手順に沿って測定しデータ品質を担保することが最重要です。測定条件が揃っているほど、AIが「いつもと違う挙動」を正確に学習できます。
振動測定結果の読み方(基準・異常の兆候)
振動測定の値をどのように解釈するかは、設備診断の質に直結します。専門的な規格やメーカー基準を参照することが理想ですが、基本的な“読み方の型”を押さえるだけでも、異常の兆候に早く気づけるようになります。ここでは、現場で最低限知っておきたい振動値の見方と、典型的な異常のパターンを整理します。
絶対値(瞬間の値)とトレンド(経時変化)で判断する
振動評価では、単に「数値が高いか低いか」だけで判断するのではなく、必ず“時間軸”とセットで評価します。単発の値が基準内でも、トレンドが上昇している場合は、異常の初期兆候である可能性があります。
- 絶対値:ISO規格・メーカー基準に照らして、安全範囲/警戒/危険レベルなどを判断する
- トレンド:同じ条件(回転数・負荷)で測った値の変化を時系列で追い、増加傾向を確認する
AIによる異常検知でも、この「トレンド情報」は重要な判断材料になります。連続データがある設備ほどAIと相性がよいのはこのためです。
典型的な異常パターンを知っておく
現場で最もよく遭遇する異常パターンはある程度決まっています。すべてを覚える必要はありませんが、「こういう症状が出たらこの可能性が高い」という大まかな対応関係を知っておくと、問題の絞り込みがスムーズになります。
- 振動速度が全体的に高い:アンバランス、据付不良、締結不足
- 軸方向の振動が大きい:ミスアライメント、スラスト荷重の問題
- 加速度の高周波成分が急増:ベアリング摩耗、潤滑不良、ギアの欠け
- 特定の回転数付近で振動が急増:共振・危険速度に近づいている可能性
- 段階的な振動上昇:劣化の進行や経年摩耗のサイン
周波数スペクトルを見ると原因が分かりやすい
時間波形(時系列データ)だけでは異常の原因を特定しにくい場合、FFT(高速フーリエ変換)を用いた周波数スペクトルを見ることで、異常の種類をより明確にできます。
- 回転数の1倍成分(1X)が強い:アンバランスの可能性が高い
- 回転数の2倍成分(2X)が強い:ミスアライメントの疑い
- 高周波帯に不規則なピーク:ベアリング異常の兆候
- ギアメッシュ周波数付近のピーク:ギア歯面の損傷や偏摩耗
AIで周波数スペクトルを入力する場合、このような特徴はモデルにとって強力な判断材料になります。逆に言えば、正しく周波数成分を取得できていないと、AI精度は大幅に低下します。
測定条件をそろえないと正しく比較できない
振動は、回転数・負荷・温度などによって大きく変わります。測定ごとに条件がバラバラだと、異常かどうかの判断が困難になります。
- 回転数(rpm)を毎回記録しておく
- 負荷率(%)や運転モードをメモしておく
- 同じ測定点・同じ方向で測る
定期点検やAI学習において、条件の一貫性は非常に重要です。振動値の「絶対的な高さ」よりも、「同じ条件でどう変化したか」を見る方が、早期発見につながりやすくなります。
振動データをAI異常検知に活かすステップ
振動測定は、AI異常検知との相性が非常に良いデータ領域です。ベアリング摩耗やギア欠けなどの初期異常は高周波のわずかな変化として現れるため、人の目では判断できない徴候もAIなら捉えられる可能性があります。しかし、AIは魔法ではなく「良質な振動データ」があって初めて高い精度を発揮します。ここでは、振動測定からAI活用へとつなげる現実的なステップを整理します。
ステップ1:巡回測定でトレンドを把握する
まずはポータブル振動計による巡回測定から始めるのが現実的です。月1回・週1回などの頻度で測定し、同じ条件での振動値を時系列で記録することで、設備ごとの「平常時の振動レベル」を把握できます。
- 最低限のコストでスタートできる
- トレンドの上昇にいち早く気づける
- AI導入の前段階として、基準データを蓄積できる
この段階で得られたデータは、その後AIを学習させる際の“正常データセット”として機能します。
ステップ2:常設センサーで連続データを集める
AIを本格的に活用するためには、より高頻度・高品質の振動データが必要です。そこで有効なのが常設型加速度センサーによる連続測定です。IoTゲートウェイを通してクラウドにデータを送れば、24時間リアルタイムで設備状態を監視できます。
- 異常発生前後の波形をそのまま記録できる
- 周波数成分の変化を詳細に追跡できる
- AIが学習しやすい“連続データ”が手に入る
特にベアリングやギアの初期異常は高周波寄りに現れるため、高帯域の加速度センサーがあるほどAI精度が向上します。
ステップ3:特徴量を整理し、AIモデルで異常スコア化する
AI異常検知では、振動データから「正常時のパターン」を学習し、そこから外れた挙動を“異常スコア”として算出します。現場で多いのは以下の2パターンです。
- 教師なし異常検知:正常データだけでモデルを作り、いつもと違う振動をスコア化する
- 教師あり学習:過去の正常・異常データをラベル付きで学習し、分類モデルを構築する
多くの現場では「異常データがほとんどない」ため、教師なし異常検知を起点に進めるケースが多く見られます。AIの入力には、時系列波形・FFT・統計量(rms、峰値、歪度など)を組み合わせると効果的です。
ステップ4:運用に組み込み、人とAIで判断する体制にする
AI異常検知は導入しただけでは効果を最大化できません。現場の判断プロセスに組み込み、「人が確認するべきサイン」を整理した運用を構築することが重要です。
- 異常スコアが急上昇した際の確認フローを定義しておく
- 波形・周波数スペクトルを人間が最後にチェックする仕組みを作る
- AIだけで判断しない“二段階判定”を整備する
人とAIが役割分担することで誤検知・過検知を防ぎ、現場で安心して使える体制が構築できます。一度仕組みが整えば、少人数でも多くの設備を効率的に管理できるようになります。
AI活用のロードマップ(まとめ)
- まずは巡回測定で最低限のデータを集める
- 重要設備には常設センサーを導入して連続データを確保する
- 正常データを基にAIで“いつもと違う”挙動をスコア化する
- 人とAIの二段階判定で運用に落とし込み、予兆保全を実現する
振動測定は、AI異常検知のための“前工程”ではなく、AIの精度を決める根幹です。良質なデータを集め、段階的にAIを取り入れていくことで、設備管理は大きく進化します。
よくある質問(FAQ)
Q. AIがあるのに、振動測定の基礎知識は必要ですか?
A. 必須です。AIはデータのパターンを学習できますが、「どこを・どの方向に・どんな条件で測るべきか」という測定設計は人間が決めなければなりません。測定条件が不適切だと、AIがいくら高度でも正しい判断ができません。振動測定の基礎知識は、AI活用の前提条件です。
Q. スマホの加速度センサーで振動測定の代用はできますか?
A. 簡易的な傾向把握なら可能ですが、設備診断レベルでは限界があります。特にベアリング異常のような高周波成分はスマホでは十分に捉えられません。予兆保全やAI解析を目指すなら、専用の加速度センサーを使うことが不可欠です。
Q. 振動データだけでAI予兆保全は成り立ちますか?
A. 多くの設備では振動だけでも一定の精度で異常検知が可能です。ただし、温度・電流・圧力など他のデータと組み合わせることでより安定した判定が行えます。まずは振動を中心に始め、必要に応じて監視項目を増やしていく段階的な導入がおすすめです。
Q. FFT(フーリエ変換)を理解していないとAI異常検知は運用できませんか?
A. 詳細な理論を理解する必要はありませんが、「回転数の何倍の周波数にピークが出るとどんな異常が疑われるか」程度の基本知識があると、AIが出した結果の妥当性を判断しやすくなります。人とAIが補完し合うためにも、FFTの初歩だけは押さえておくと良いです。
Q. 既存の振動監視システムがある場合でも、AI導入の余地はありますか?
A. あります。既存のしきい値監視に加えてAIの異常スコアを参考にすることで、「しきい値未満だが挙動が怪しい」などの微妙な変化を拾えるようになります。既存システムのデータをそのままAI学習に活用できる場合も多く、追加投資を抑えながら精度を高める方法として現実的です。
Q. 異常が検出された際、必ず設備を止める必要がありますか?
A. 異常度によります。AIが異常スコアを出した時点では「変化が見られた」という段階であり、すぐに停止判断する必要はありません。まずは波形や周波数スペクトルを確認し、必要に応じて現場確認や追加測定を行います。AIの提示はあくまで“気づくためのサイン”として扱うことが重要です。
まとめ
- 振動測定は、設備の初期異常を捉えるための最も基本かつ効果的な技術であり、予防保全や予兆保全の土台となる。
- 振動の評価には「変位・速度・加速度」の3つの物理量があり、それぞれ得意とする異常や用途が異なる。
- 測定点・方向・周波数帯・サンプリング条件の設計は、データの精度とAIの学習効果を左右する最重要ポイント。
- 振動結果の“絶対値”だけでなく“トレンドの変化”を追うことで、故障予兆をより早く把握できる。
- AI異常検知は、振動データとの相性が良く、巡回測定→常設センサー→AI分析という段階的導入が最も現実的で効果的。
振動測定の基本をきちんと押さえることで、従来の経験・勘に頼った点検から、データに基づいた設備管理へとステップアップできます。そして、その延長線上にAIによる予兆保全があり、適切な測定設計とデータ蓄積ができていれば、AIは驚くほど頼もしい“第二の目”として機能します。まずはできる範囲の測定から始め、段階的にAI活用へとつなげていくことで、故障リスクの低減と保全の効率化を同時に実現できるようになります。
romptn ai厳選のおすすめ無料AIセミナーでは、AIの勉強法に不安を感じている方に向けた内容でオンラインセミナーを開催しています。
AIを使った副業の始め方や、収入を得るまでのロードマップについて解説しているほか、受講者の方には、ここでしか手に入らないおすすめのプロンプト集などの特典もプレゼント中です。
AIについて効率的に学ぶ方法や、業務での活用に関心がある方は、ぜひご参加ください。
\累計受講者10万人突破/