 画像生成AI
画像生成AI 【2026最新】SeaArtプロンプトの書き方完全ガイド!基本から応用、活用法まで徹底解説
SeaArtを使い始めたものの、「プロンプトってどう書けばいいの?」と悩んでいませんか?実際に使ってみると、「思ったような画像が出ない」、「Stable Diffusionの書き方と同じでいいの?」と感じる人は少なくありません。AI画像生成...
 画像生成AI
画像生成AI  クリエイティブAIツール
クリエイティブAIツール  AI副業・学習
AI副業・学習 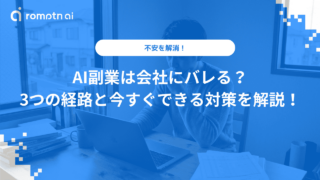 AI副業・学習
AI副業・学習 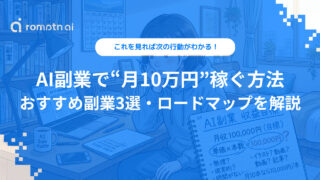 未分類
未分類  画像生成AI
画像生成AI  画像生成AI
画像生成AI  未分類
未分類  画像生成AI
画像生成AI  画像生成AI
画像生成AI